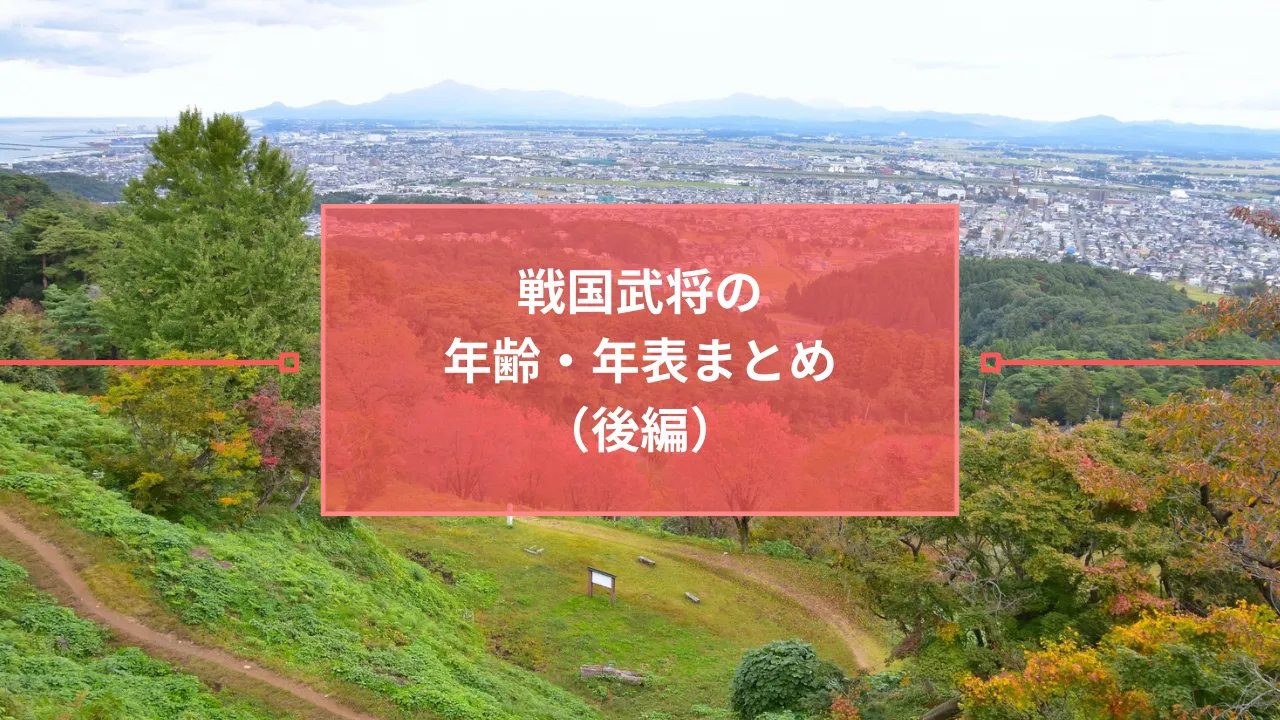目次
- 1 1544年(天文13年)
- 2 1545年(天文14年)
- 3 1546年(天文15年)
- 4 1547年(天文16年)
- 5 1548年(天文17年)
- 6 1550年(天文20年)
- 7 1553年(天文22年)
- 8 1555年(天文24年)
- 9 1556年(弘治2年)
- 10 1557年(弘治3年)
- 11 1559年(永禄2年)
- 12 1560年(永禄3年)
- 13 1561年(永禄4年)
- 14 1562年(永禄5年)
- 15 1563年(永禄6年)
- 16 1566年(永禄9年)
- 17 1567年(永禄10年)
- 18 1568年(永禄11年)
- 19 1571年(元亀2年)
- 20 1573年(元亀4年)
- 21 1575年(天正3年)
- 22 1576年(天正4年)
- 23 1577年(天正5年)
- 24 1578年(天正6年)
- 25 1579年(天正7年)
- 26 1582年(天正10年)
- 27 1584年(天正12年)
- 28 1585年(天正13年)
- 29 1586年(天正14年)
- 30 1587年(天正15年)
- 31 1588年(天正16年)
- 32 1590年(天正18年)
- 33 1593年(文禄2年)
- 34 1597年(慶長2年)
- 35 1598年(慶長3年)
- 36 1599年(慶長4年)
- 37 1600年(慶長5年)
- 38 1602年(慶長7年)
- 39 1603年(慶長8年)
- 40 1604年(慶長9年)
- 41 1605年(慶長10年)
- 42 1606年(慶長11年)
- 43 1610年(慶長15年)
- 44 1611年(慶長16年)
- 45 1614年(慶長19年)
- 46 1615年(慶長20年)
- 47 今日の記事:まとめると意外と楽しいですね
1544年(天文13年)
| 斎藤道三 | 50歳 |
| 毛利元就 | 47歳 |
| 北条氏康 | 29歳 |
| 今川義元 | 25歳 |
| 武田信玄 | 23歳 |
| 毛利隆元 | 21歳 |
| 明智光秀 | 16歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 14歳 |
| 小早川隆景 | 11歳 |
| 織田信長 | 10歳 |
| 島津義弘 | 9歳 |
| 佐々成政 | 8歳 |
| 豊臣秀吉 | 7歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 6歳 |
| 長宗我部元親 | 5歳 |
| 徳川家康 | 1歳 |
竹中半兵衛誕生
豊臣秀吉に仕えた名参謀。一時期黒田官兵衛と共に秀吉に仕え「両兵衛」ともうたわれていました。
しかし織田信長に対して荒木村重が謀反を起こした際に説得に行った黒田官兵衛が幽閉され、官兵衛も裏切ったと勘違いした信長は官兵衛の子で人質だった松寿丸(後の黒田長政)を殺すよう命令するが官兵衛が裏切ってないと確信していた半兵衛は奇策を用いて命をかけて松寿丸を守った。
その後陣中にて病を患い官兵衛帰還を見届けることができないまま1579年、35歳の若さで死去しました。
隆景が竹原小早川家に養子入り
竹原小早川家当主・小早川興景が病死。
世継ぎがいなかったことから、竹原小早川家の家臣団は毛利元就に三男・隆景を養子として迎え入れ、竹原小早川家の後継にしたいと要求してきた。
紆余曲折あったが、結果的に元就は養子要求を承諾。
隆景は1544年(天文13年)11月に竹原小早川家に養子として入り、11歳(当時の数え年で12歳)で竹原小早川家の当主となる。
1545年(天文14年)
| 斎藤道三 | 51歳 |
| 毛利元就 | 48歳 |
| 北条氏康 | 30歳 |
| 今川義元 | 26歳 |
| 武田信玄 | 24歳 |
| 毛利隆元 | 22歳 |
| 明智光秀 | 17歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 15歳 |
| 小早川隆景 | 12歳 |
| 織田信長 | 11歳 |
| 島津義弘 | 10歳 |
| 佐々成政 | 9歳 |
| 豊臣秀吉 | 8歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 7歳 |
| 長宗我部元親 | 6歳 |
| 徳川家康 | 2歳 |
| 竹中半兵衛 | 1歳 |
山内一豊誕生
父は元々岩倉織田に仕えていたが、織田信長と対立し結果岩倉城は落城し自刃した。
一豊は諸国を放浪した後に信長に仕えて秀吉の与力となりその後は秀吉がなくなるまで仕えた。秀吉死後は徳川家康に与して東軍として関ヶ原の戦いに参戦し勝利。
小山評定などのその貢献度を評価され長宗我部家の旧領であった土佐20万石を拝領し土佐国主となった。妻は黄金10両で馬を購入させたなどの逸話が残り内助の功で知られる千代(見性院)。
1546年(天文15年)
| 斎藤道三 | 52歳 |
| 毛利元就 | 49歳 |
| 北条氏康 | 31歳 |
| 今川義元 | 27歳 |
| 武田信玄 | 25歳 |
| 毛利隆元 | 23歳 |
| 明智光秀 | 18歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 16歳 |
| 小早川隆景 | 13歳 |
| 織田信長 | 12歳 |
| 島津義弘 | 11歳 |
| 佐々成政 | 10歳 |
| 豊臣秀吉 | 9歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 8歳 |
| 長宗我部元親 | 7歳 |
| 徳川家康 | 3歳 |
| 竹中半兵衛 | 2歳 |
| 山内一豊 | 1歳 |
武田勝頼誕生
元々は側室の子で四男だったことから家督相続権がなかったが義信の廃嫡など様々な要因が重なり後継者として指名されました。
そして1573年に西上作戦の陣中でなくなった武田信玄の跡を継いで27歳の時に武田家当主となり武田家を率いました。
武勇に優れた武将として評価されていたが長篠の戦いで織田・徳川連合軍の鉄砲隊の前に信玄時代より仕えていた多くの重臣たちを失い敗戦したことで勢力が後退。
その後も一定の勢力は保っていたものの甲州征伐によって執拗に責められ、譜代の重臣たちの裏切りにもあって1582年(天正10年)に天目山の戦いで敗れ戦死。これにより甲斐武田家は滅亡。
信玄が死去してから9年後のことでした。
黒田官兵衛誕生
戦国三英傑である織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の3名に一目置かれた名将。
秀吉が3日かけて考え抜いた策を瞬時に考え出すなど知恵が回り長らく秀吉の下で軍師として使えましたがその知恵の回り具合から天下人として邁進する秀吉に警戒され次第に距離を置かれるようになりました。
小早川隆景とは敵味方とはいえ中国攻めの際からの顔なじみであり、隆景は官兵衛に「良い策が浮かんだ時こそ吟味するように」とアドバイスしたと言われ官兵衛の子・長政にも様々なアドバイスをしたと言われるなど非常に懇意な仲だったとされる。
1597年に隆景が死去した際は「この国に賢人はいなくなった」と嘆いたと言われています。
1547年(天文16年)
| 斎藤道三 | 53歳 |
| 毛利元就 | 50歳 |
| 北条氏康 | 32歳 |
| 今川義元 | 28歳 |
| 武田信玄 | 26歳 |
| 毛利隆元 | 24歳 |
| 明智光秀 | 19歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 17歳 |
| 小早川隆景 | 14歳 |
| 織田信長 | 13歳 |
| 島津義弘 | 12歳 |
| 佐々成政 | 11歳 |
| 豊臣秀吉 | 10歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 9歳 |
| 長宗我部元親 | 8歳 |
| 徳川家康 | 4歳 |
| 竹中半兵衛 | 3歳 |
| 山内一豊 | 2歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 1歳 |
真田昌幸誕生
武田信玄に仕えた真田幸隆の3男。元々は3男のため家督相続権はなく武藤家に養子に出され武藤喜兵衛として、信玄に仕え三方ヶ原の戦いなど多くの戦に参戦した。
しかし長篠の戦いで2人の兄であった真田信綱・昌輝が戦死したため真田家に戻り真田昌幸と名乗って真田家の家督を継いだ。
その後も信玄に仕え信玄亡き後は子の勝頼に仕えるも織田信長の甲州征伐によって勝頼は戦死し武田家は滅亡。滅亡後は織田家の軍門に下るも3か月後に本能寺の変で信長が横死し再び独立した。
その後は豊臣秀吉に仕えて天下取りに協力。秀吉死去後ははじめ家康に与するも途中で石田三成に与して徳川秀忠率いる徳川本隊を上田城にて足止めし、折からの長雨もあって関ヶ原の戦いへの遅参を成功させた。
しかし予想に反して関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍が勝利し三成は切腹。
東軍に与していた長男・信之と信之の義父である徳川四天王の1人本多忠勝の命乞いもあって死罪は免れるも領地と兵すべてを奪われ次男の真田幸村と共に九度山に幽閉され関ケ原の戦いから11年後、大阪冬の陣が勃発する3年前の1611年に64歳で死去した。
昌幸の想いは次男・幸村に受け継がれ幸村は大阪冬の陣・夏の陣に参陣することとなります。
元春が吉川家に養子入り
元就の次男・元春が母方の従兄・吉川興経の養子として吉川家に入り、吉川元春と名乗るようになる。
興経には子息・千法師がいたが、興経と仲が悪かった叔父・吉川経世をはじめとする家臣団の勧めもあり、興経は「興経の生命の保障」「千法師を元春の養子とし、成長後に吉川家の家督を相続させること」の2つを条件にやむなく養子を承服した。
1548年(天文17年)
| 斎藤道三 | 54歳 |
| 毛利元就 | 51歳 |
| 北条氏康 | 33歳 |
| 今川義元 | 29歳 |
| 武田信玄 | 27歳 |
| 毛利隆元 | 25歳 |
| 明智光秀 | 20歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 18歳 |
| 小早川隆景 | 15歳 |
| 織田信長 | 14歳 |
| 島津義弘 | 13歳 |
| 佐々成政 | 12歳 |
| 豊臣秀吉 | 11歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 10歳 |
| 長宗我部元親 | 9歳 |
| 徳川家康 | 5歳 |
| 竹中半兵衛 | 4歳 |
| 山内一豊 | 3歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 2歳 |
| 真田昌幸 | 1歳 |
榊原康政誕生
徳川四天王の1人であり同じく四天王の本多忠勝とは同級生で家康の天下稼業を支えた。
生涯戦で手傷を負ったことのない本多忠勝には武勇では負けるが指揮官としては一流でその能力は本多忠勝を上回り井伊直政に匹敵するとも言われ、行政能力にも長けていることから弱点という弱点が存在しないオールマイティな武将です。
本多忠勝誕生
徳川四天王の1人であり同じく四天王の1人であった榊原康政とは同級生で主君・家康に仕え終生仕え活躍した。
生涯参陣した戦で手傷を負ったことのない勇猛果敢で武勇誉れな猛将。
内政手腕にも長けており関ケ原の戦いにて桑名藩を拝領した際は藩体制を確保するために町割りや城の修繕など努め桑名藩創成の名君ともいわれています。
1610年に死去したが1603年に江戸幕府が開いたころから徳川家中では本多正純などの文治派が台頭。
忠勝自身も1604年頃から病がちだったことから、晩年期は中枢から遠ざかっていたそうです。
1550年(天文20年)
| 斎藤道三 | 56歳 |
| 毛利元就 | 53歳 |
| 北条氏康 | 35歳 |
| 今川義元 | 31歳 |
| 武田信玄 | 29歳 |
| 毛利隆元 | 27歳 |
| 明智光秀 | 22歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 20歳 |
| 小早川隆景 | 17歳 |
| 織田信長 | 16歳 |
| 島津義弘 | 15歳 |
| 佐々成政 | 14歳 |
| 豊臣秀吉 | 13歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 12歳 |
| 長宗我部元親 | 11歳 |
| 徳川家康 | 7歳 |
| 竹中半兵衛 | 6歳 |
| 山内一豊 | 5歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 4歳 |
| 真田昌幸 | 3歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 2歳 |
吉川家の相続・乗っ取り
吉川興経を強制的に隠居させて、吉川元春が吉川家当主となる。
次いで、興経と千法師を殺害し、吉川家の乗っ取りに成功した。
これはすべて毛利元就の調略であったといわれています。
沼田小早川家の乗っ取り・小早川家の統合
毛利元就と大内義隆が共謀し、沼田小早川家当主・小早川繁平を隠居・出家させて追放。
竹原小早川家の当主となっていた隆景と繁平の妹を婚姻させ、乗っ取る形で隆景を沼田小早川家の当主にし、沼田小早川家・竹原小早川家を統合させた。
乗っ取りに際して、繫平派の重臣を多く粛清し、小早川家を手中に収めることに成功。
吉川家・小早川家を手中に収めたことで、毛利両川(もうりりょうせん)体制の基盤ができあがりました。
1553年(天文22年)
| 斎藤道三 | 59歳 |
| 毛利元就 | 56歳 |
| 北条氏康 | 38歳 |
| 今川義元 | 34歳 |
| 武田信玄 | 32歳 |
| 毛利隆元 | 30歳 |
| 明智光秀 | 25歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 23歳 |
| 小早川隆景 | 20歳 |
| 織田信長 | 19歳 |
| 島津義弘 | 18歳 |
| 佐々成政 | 17歳 |
| 豊臣秀吉 | 16歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 15歳 |
| 長宗我部元親 | 14歳 |
| 徳川家康 | 10歳 |
| 竹中半兵衛 | 9歳 |
| 山内一豊 | 8歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 7歳 |
| 真田昌幸 | 6歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 5歳 |
毛利輝元誕生
安芸の国の戦国大名・毛利隆元の長男。祖父は一時代で中国地方を制覇したとされる知将・毛利元就。
父である隆元が40歳という若さで急死したため、11歳で毛利家当主となる。しかし若年のため祖父の毛利元就が後見となり実権を握っていた。
元就自身は、輝元を補佐しつつ徐々に輝元に権限委譲して隠居するつもりであったが輝元が頑なに拒んだため、元就が死去するまでこの体制が維持されることになったそうです。
元就死後は叔父の吉川元春・小早川隆景が中心となった毛利両川体制の補佐のもと、領国運営にまい進していきます。
その後は尾張の織田信長との対立、本能寺の変後は豊臣秀吉と親交を深め五大老に任命されるまでの信頼を得ます。
しかし、「毛利は天下を望んではならない」という祖父・元就と「中央の争いに参加してはならない。」という叔父・小早川隆景の遺言を破って、関ケ原の戦いに西軍として参加し敗退。
吉川元春の3男・広家の必死の助命嘆願の末死罪は免れるも、安芸を中心とした山陽・山陰8か国の約120万石から周防・長門2ヶ国の約29万石に大減俸され祖父・元就が築いた旧領をほぼ全て失う結果となりました。
周防・長門2ヶ国の約29万石への大減俸、関ヶ原の戦いでの敗戦などもあり、長男の秀就に家督譲っていたため、初代・長州藩主は秀就とされ輝元は藩祖という位置になっています。
しかし形式に家督を譲っただけであり、実質的には輝元が実権を握った二頭政治だったようです。
聖徳寺の会見
尾張の大うつけ・織田信長が義父である美濃のマムシ・斎藤道三と会合したことで有名な聖徳寺の会見が行われたのが1553年。実に信長19歳、道三59歳の時。
信長公記によると会見に向かう信長軍に加わった弓・鉄砲隊は500挺であったとされている。
鉄砲と弓の割方がどれくらいは定かではないが、種子島に鉄砲が伝わってからわずか10年しかたっておらず合戦用の武器として一般的にまだ定着していない時期であった。
にもかかわらず、いち早くその優位性を見抜き、鉄砲を装備した信長軍を見て、美濃のマムシもさすがに驚嘆したとされる。
この会見は度々ドラマで映像化されているため有名で、明智光秀を主人公に据え俳優の長谷川博己さんが明智光秀を演じる2020年大河ドラマ「麒麟がくる」の第14回のタイトルにもなっています。
1555年(天文24年)
| 斎藤道三 | 61歳 |
| 毛利元就 | 58歳 |
| 北条氏康 | 40歳 |
| 今川義元 | 36歳 |
| 武田信玄 | 34歳 |
| 毛利隆元 | 32歳 |
| 明智光秀 | 27歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 25歳 |
| 小早川隆景 | 22歳 |
| 織田信長 | 21歳 |
| 島津義弘 | 20歳 |
| 佐々成政 | 19歳 |
| 豊臣秀吉 | 18歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 17歳 |
| 長宗我部元親 | 16歳 |
| 徳川家康 | 12歳 |
| 竹中半兵衛 | 11歳 |
| 山内一豊 | 10歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 9歳 |
| 真田昌幸 | 8歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 7歳 |
| 毛利輝元 | 2歳 |
厳島の戦い
主君・大内義隆を討ち大内家の実権を握っていた陶晴賢と毛利元就との間で行われた戦い。
陶軍の総勢は約2~3万人に対して毛利軍は約4000~5000人と数では圧倒的に毛利が不利な状況であった。
しかし巧みな外交戦略で村上水軍を味方につけ、嵐にもかかわらず船で厳島に渡り陶軍を急襲するという鮮やかな奇襲で陶軍を撃破しました。
この戦いで陶晴賢は戦死。陶を失った大内家は急速に弱体化することになります。
1556年(弘治2年)
| 斎藤道三 | 死去(62歳) |
| 毛利元就 | 59歳 |
| 北条氏康 | 41歳 |
| 今川義元 | 37歳 |
| 武田信玄 | 35歳 |
| 毛利隆元 | 33歳 |
| 明智光秀 | 28歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 26歳 |
| 小早川隆景 | 23歳 |
| 織田信長 | 22歳 |
| 島津義弘 | 21歳 |
| 佐々成政 | 20歳 |
| 豊臣秀吉 | 19歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 18歳 |
| 長宗我部元親 | 17歳 |
| 徳川家康 | 13歳 |
| 竹中半兵衛 | 12歳 |
| 山内一豊 | 11歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 10歳 |
| 真田昌幸 | 9歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 8歳 |
| 毛利輝元 | 3歳 |
長良川の戦い
下剋上大名の代名詞でもある美濃のマムシ・斎藤道三と道三の息子で長男の斎藤義龍との間で起こった父子同士の戦い。
この戦いで斎藤道三は戦死し、名実ともに義龍が美濃の最高権力者になった。
この戦いは近隣諸国にも大きな影響を及ぼし、道三の娘・帰蝶(濃姫)が嫁いでいた尾張の織田家にも影響が波及していくことになります。
1557年(弘治3年)
| 毛利元就 | 60歳 |
| 北条氏康 | 42歳 |
| 今川義元 | 38歳 |
| 武田信玄 | 36歳 |
| 毛利隆元 | 34歳 |
| 明智光秀 | 29歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 27歳 |
| 小早川隆景 | 24歳 |
| 織田信長 | 23歳 |
| 島津義弘 | 22歳 |
| 佐々成政 | 21歳 |
| 豊臣秀吉 | 20歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 19歳 |
| 長宗我部元親 | 18歳 |
| 徳川家康 | 14歳 |
| 竹中半兵衛 | 13歳 |
| 山内一豊 | 12歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 11歳 |
| 真田昌幸 | 10歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 9歳 |
| 毛利輝元 | 4歳 |
織田信忠誕生
戦国三英傑の1人である織田信長の長男(信正が実在すれば次男)として尾張国で誕生。
信長の後継者として父に従い、石山合戦や伊勢長島攻め、長篠の戦いなど多くの戦場を転戦。
1582年(天正10年)の甲州征伐では総大将として武田領を侵攻し武田勝頼を自害させ武田家を滅亡させる戦果を挙げる。
しかしその3ヶ月後に起こった本能寺の変にて明智光秀に強襲され父・信長が自害。
同じく京都の妙覚寺を宿にしていた信忠自身も明智勢に攻め込まれ自害した。
歴史にもしもはないが、信忠が死去せず生き延びていれば豊臣秀吉の天下はなかったとされている。
防長経略の完了
厳島の戦いで大内家の主力・陶晴賢を打ち破った毛利元就が1555年から実施していた周防・長門への侵攻作戦。
約2年にも及ぶ侵攻の末、追い込まれた大内家当主・大内義長は自害。
大内と陶の両家の後継者が途絶えたことで、毛利家は大内が支配していた周防・長門などを含めて広大な領地を手にし、戦国の大大名となりました。
1559年(永禄2年)
| 毛利元就 | 62歳 |
| 北条氏康 | 44歳 |
| 今川義元 | 40歳 |
| 武田信玄 | 38歳 |
| 毛利隆元 | 36歳 |
| 明智光秀 | 31歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 29歳 |
| 小早川隆景 | 26歳 |
| 織田信長 | 25歳 |
| 島津義弘 | 24歳 |
| 佐々成政 | 23歳 |
| 豊臣秀吉 | 22歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 21歳 |
| 長宗我部元親 | 20歳 |
| 徳川家康 | 16歳 |
| 竹中半兵衛 | 15歳 |
| 山内一豊 | 14歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 13歳 |
| 真田昌幸 | 12歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 11歳 |
| 毛利輝元 | 6歳 |
| 織田信忠 | 2歳 |
直江兼続誕生
愛という文字を兜に掲げていたことで有名で「義」を重んじたとされる戦国武将。
上杉景勝の家臣で懐刀ともいうべき人物。
石田三成とは非常に親しい関係を築いたようです。上杉景勝を終生支え、関ヶ原の戦いでは盟友・石田三成を助け西軍に与するも敗戦し石田三成は死罪。
敗退後は景勝とともに家康に謝罪し死罪は免れるも秀吉から拝領した会津120万石から米沢30万石に大減俸させられる。しかし家臣をリストラさせず経済手腕などを発揮して領国安定の為に尽力した。
1560年(永禄3年)
| 毛利元就 | 63歳 |
| 北条氏康 | 45歳 |
| 今川義元 | 死去(41歳) |
| 武田信玄 | 39歳 |
| 毛利隆元 | 37歳 |
| 明智光秀 | 32歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 30歳 |
| 小早川隆景 | 27歳 |
| 織田信長 | 26歳 |
| 島津義弘 | 25歳 |
| 佐々成政 | 24歳 |
| 豊臣秀吉 | 23歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 22歳 |
| 長宗我部元親 | 21歳 |
| 徳川家康 | 17歳 |
| 竹中半兵衛 | 16歳 |
| 山内一豊 | 15歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 14歳 |
| 真田昌幸 | 13歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 12歳 |
| 毛利輝元 | 7歳 |
| 織田信忠 | 3歳 |
| 直江兼続 | 1歳 |
石田三成誕生
豊臣秀吉の家臣で佐和山城主。豊臣家の奉行・秀吉死後は五奉行の1人として活躍した。
秀吉が中国攻めの総司令官として毛利を攻めてはじめた頃には既に秀吉に仕えて従軍していたようです。
豊臣家臣団の中で三成が頭角を表すのは、信長が本能寺の変で死去し秀吉が後継者として天下統一を目指し始めた頃からです。
その後は奉行として秀吉の天下統一事業を支え続けました。しかし秀吉が死去すると福島正則・加藤清正といった武断派と三成など奉行を中心とした文治派が対立を深めます。
その間に立って仲裁を図っていた前田利家も死去すると、対立は激化しその争いに漬け込まれ徳川家康の台頭を許るし関ヶ原の戦いにて家康に敗れて死罪となった。
桶狭間の戦い
織田信長と今川義元の間で起きた戦い。
総勢が約2万5000人とも言われる今川軍に対し、たった2000人で奇襲し織田軍が勝利。
この戦いで今川軍は今川義元をはじめ有力な家臣が戦死。織田家の台頭と今川家弱体化の分水嶺になった。
日本三大奇襲の1つに数えられる戦いで、歴史上最も有名な戦いの1つです。
1561年(永禄4年)
| 毛利元就 | 64歳 |
| 北条氏康 | 46歳 |
| 武田信玄 | 40歳 |
| 毛利隆元 | 38歳 |
| 明智光秀 | 33歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 31歳 |
| 小早川隆景 | 28歳 |
| 織田信長 | 27歳 |
| 島津義弘 | 26歳 |
| 佐々成政 | 25歳 |
| 豊臣秀吉 | 24歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 23歳 |
| 長宗我部元親 | 22歳 |
| 徳川家康 | 18歳 |
| 竹中半兵衛 | 17歳 |
| 山内一豊 | 16歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 15歳 |
| 真田昌幸 | 14歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 13歳 |
| 毛利輝元 | 8歳 |
| 織田信忠 | 4歳 |
| 直江兼続 | 2歳 |
| 石田三成 | 1歳 |
福島正則誕生
秀吉子飼いの武将で本能寺の変で信長の死後に起こった賤ヶ岳の戦いにて活躍した賤ヶ岳の七本槍の1人。
秀吉家臣団きっての猛将として活躍。秀吉死後は文治派の石田三成らと対立し徳川家康に与して東軍として関ヶ原の戦いに参加した。
関ヶ原の戦い勝利後は毛利家の領地であった安芸・備後約150万石を拝領し広島城に入城して統治した。
しかし家康死後の1619年に台風によって破損した広島城の一部を修復したが、無断修復ということで武家諸法度違反を疑われ、安芸・備後150万国を没収させられた。
没収させた安芸・備後は浅野氏が拝領し、幕末で統治されていくことになります。
井伊直政誕生
徳川四天王や徳川三傑などに数えられる1人で、井伊の赤備えとしても知られる文武両道に長けた戦国武将。
家康の天下取りを献身的に支えた家臣として現在でも称えられている。
関ヶ原の戦いにて島津軍を追撃するも狙撃され大けがを負うが、関ヶ原の戦後処理と江戸幕府の基礎固めにまい進する。
毛利家や島津家をはじめ、長宗我部、真田昌幸・信繁(幸村)といった西軍に加担した多くの戦国武将の和平交渉・助命に尽力したとされる。
そのような活躍・貢献が認められ、石田三成の旧領である佐和山(現:彦根市(彦根藩))18万石を拝領する。家康が直政を彦根に配置した理由として、西国諸藩の抑えと有事の際に朝廷を保護があったとされその信頼度が伺えます。
しかし鉄砲傷による大怪我の療養もままならぬ中で戦後処理・幕府の基礎固めと多忙を極め無理したために薬石効なく関ヶ原での傷が元で42歳の若さで死去した。
その後は井伊家は明治時代になるまで彦根藩を統治。有名な子孫には幕末において安政の大獄を起こし、桜田門外の変で暗殺された井伊直弼がいます。
1562年(永禄5年)
| 毛利元就 | 65歳 |
| 北条氏康 | 47歳 |
| 武田信玄 | 41歳 |
| 毛利隆元 | 39歳 |
| 明智光秀 | 34歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 32歳 |
| 小早川隆景 | 29歳 |
| 織田信長 | 28歳 |
| 島津義弘 | 27歳 |
| 佐々成政 | 26歳 |
| 豊臣秀吉 | 25歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 24歳 |
| 長宗我部元親 | 23歳 |
| 徳川家康 | 19歳 |
| 竹中半兵衛 | 18歳 |
| 山内一豊 | 17歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 16歳 |
| 真田昌幸 | 15歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 14歳 |
| 毛利輝元 | 9歳 |
| 織田信忠 | 5歳 |
| 直江兼続 | 3歳 |
| 石田三成 | 2歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 1歳 |
北条氏直誕生
北条早雲からつづく北条家5代目にして最後の当主。5代目であるが実質的な権力は父であり4代目当主の北条氏政が握っていた。
本能寺の変び信長死去で混乱する武田旧領であった甲斐(山梨県)・信濃(長野県)に侵攻し領土拡大を進めた。
その後信長の跡を継いだ秀吉が天下をほぼ手中に収める中で、秀吉の上洛要請や天下惣無事令をことごとく無視し真田昌幸が納める城を攻めたことがきっかけで小田原城の戦いが起こる。
当初は大軍だと食糧がすぐに尽きることや、徳川家康や伊達政宗の援軍などが期待できたため、上杉謙信をも撤退された難攻不落の小田原城に立てこもり籠城策を取った。
しかし天下をほぼ手中に収めた秀吉は20万の大軍で進軍、支城を次々と攻略され完全に包囲されたばかりか石垣山に城を築く徹底抗戦の構えを取られました。
さらに伊達政宗が秀吉に降伏し、家康も援軍に来ないことを悟り和睦交渉の末開城。氏政は切腹、氏直は高野山へ幽閉され翌年病死した。
この戦いで北条家は滅亡、秀吉は天下統一を成し遂げることになりました。
加藤清正誕生
秀吉子飼いの戦国武将で福島正則らと並ぶ、賤ヶ岳の七本槍の1人。
豊臣秀吉に従い各地を転戦し武功を上げ秀吉の天下取りを支え、九州攻めの後に肥後半国を拝領する。
秀吉が死去すると文治派の石田三成らと対立。徳川家康と親交を深めて関ヶ原の戦いでは東軍として参加し戦後その活躍が認められて肥後一国と豊後国の一部を拝領して熊本藩主となった。
藤堂高虎や黒田官兵衛と並んで築城の名手でもあったとされています。
1563年(永禄6年)
| 毛利元就 | 66歳 |
| 北条氏康 | 48歳 |
| 武田信玄 | 42歳 |
| 毛利隆元 | 死去(40歳) |
| 明智光秀 | 35歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 33歳 |
| 小早川隆景 | 30歳 |
| 織田信長 | 29歳 |
| 島津義弘 | 28歳 |
| 佐々成政 | 27歳 |
| 豊臣秀吉 | 26歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 25歳 |
| 長宗我部元親 | 24歳 |
| 徳川家康 | 20歳 |
| 竹中半兵衛 | 19歳 |
| 山内一豊 | 18歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 17歳 |
| 真田昌幸 | 16歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 15歳 |
| 毛利輝元 | 10歳 |
| 織田信忠 | 6歳 |
| 直江兼続 | 4歳 |
| 石田三成 | 3歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 2歳 |
白鹿城の戦い
尼子家を攻略するために、毛利元就は尼子領に侵攻。
第二次月山富田城の戦いの前哨戦と位置づけられるのが、白鹿城の戦いです。
この戦いの最中、大友家と和睦を結び九州から元就率いる本隊に合流するはずだった毛利隆元が道中で急死。
隆元の死をきっかけに尼子を撃滅するという意思の元、士気が高まった毛利軍は白鹿城を攻略した。
食糧の補給路において重要拠点だった白鹿城が落ちたことで、月山富田城は孤立していくことになります。
毛利隆元急死
尼子領に侵攻していた毛利軍でしたが大友家が九州の毛利領を攻めたことで毛利隆元は毛利本軍から離れ九州戦線を受け持っていました。
隆元は幕府の仲介で大友家と和睦。
和睦後、尼子攻めを行っていた毛利本軍に合流する途上で急死した。
訃報を聞いた元就の悲嘆は凄まじかったそうです。隆元を死は病死とも暗殺とも言われており、その死は謎に包まれています。
1566年(永禄9年)
| 毛利元就 | 69歳 |
| 北条氏康 | 51歳 |
| 武田信玄 | 45歳 |
| 明智光秀 | 38歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 36歳 |
| 小早川隆景 | 33歳 |
| 織田信長 | 32歳 |
| 島津義弘 | 31歳 |
| 佐々成政 | 30歳 |
| 豊臣秀吉 | 29歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 28歳 |
| 長宗我部元親 | 27歳 |
| 徳川家康 | 23歳 |
| 竹中半兵衛 | 22歳 |
| 山内一豊 | 21歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 20歳 |
| 真田昌幸 | 19歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 18歳 |
| 毛利輝元 | 13歳 |
| 織田信忠 | 9歳 |
| 直江兼続 | 7歳 |
| 石田三成 | 6歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 5歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 4歳 |
真田信之誕生
真田昌幸の長男で真田幸村(信繁)は実弟。
父・昌幸は真田家の三男であり武藤家に養子に出ていたため信之は武藤家の跡取りであった。
しかし長篠の戦いにて昌幸の兄で信之には叔父にあたる信綱・昌輝が揃って戦死したために昌幸が真田に復姓したために信之も真田家の跡取りとなった。
本能寺の変の信長死去によって武田家旧領で起きた混乱では父・昌幸に従って武功を上げる。
その後も昌幸に従って転戦し、豊臣秀吉に臣従後は秀吉の天下統一事業を助けた。
秀吉の死後、石田三成と徳川家康の対立が深まると、犬伏にて石田方につく父・弟と別れ信之は義父の本多忠勝に従い徳川家康に与した。
当時としては長生きで93歳まで生き太平の世となった江戸時代において貴重な戦国時代経験者であり、家康の十男・徳川頼宣は信之の事を非常に尊敬していたようです。
しかし30代ごろは頻繁に体調を崩しており、家督を譲っていた息子たちも早世してお家騒動に発展するなど決して順風満帆な老後ではなかった。
第二次月山富田城の戦い終結
1563年(永禄6年)の白鹿城の戦いで、補給路のメインとなる白鹿城を攻略した毛利軍は尼子の拠点を次々と攻略。
残るは月山富田城のみとなる。元就は最初総攻撃を仕掛けて攻略しようとするも力攻めでは攻略不可能と判断し、包囲戦に戦略を転換。
この戦略転換が功を奏し、1566年ついに月山富田城は陥落し開城したことで1565年から続いた第二次月山富田城が終結した。
大内家に続いて尼子家を下した毛利元就は尼子領をも取り込み中国地方・最大の戦国大名に成長。
ちなみにこの戦いで、毛利輝元と吉川元春の長男・吉川元長が初陣を飾っています。
1567年(永禄10年)
| 毛利元就 | 70歳 |
| 北条氏康 | 52歳 |
| 武田信玄 | 46歳 |
| 明智光秀 | 39歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 37歳 |
| 小早川隆景 | 34歳 |
| 織田信長 | 33歳 |
| 島津義弘 | 32歳 |
| 佐々成政 | 31歳 |
| 豊臣秀吉 | 30歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 29歳 |
| 長宗我部元親 | 28歳 |
| 徳川家康 | 24歳 |
| 竹中半兵衛 | 23歳 |
| 山内一豊 | 22歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 21歳 |
| 真田昌幸 | 20歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 19歳 |
| 毛利輝元 | 14歳 |
| 織田信忠 | 10歳 |
| 直江兼続 | 8歳 |
| 石田三成 | 7歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 6歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 5歳 |
| 真田信之 | 1歳 |
伊達政宗誕生
アニメなどの効果などもあり現代で1,2を争うほど有名で人気のある戦国武将。
豊臣秀吉の小田原城侵攻に際して同盟関係であった北条家に援軍にいくか迷うが、結局豊臣秀吉に頭を下げて臣従を誓った。
秀吉の死後は徳川家康と近を通じ、最終的には仙台藩62万石になった。これは加賀・前田家、薩摩・島津家に次ぐ第3位の石高であったとされる。
江戸幕府3代将軍である徳川家光は伊達政宗を非常に尊敬しており、政宗死去に際して父の秀忠が亡くなった時以上に狼狽し嘆いたとされています。
真田幸村誕生
アニメなどの効果もあり現代では伊達政宗と並んで有名で人気な戦国武将。
真田昌幸の次男であり、実兄には信之がいます。
上杉の人質や豊臣家の人質と出されていたこともあります。特に秀吉は可愛がれたそうでその証拠に秀吉の馬廻衆に任命されたり、豊臣家のきっての知将・大谷吉継の娘を妻に迎えたりしています。
秀吉の死後は父・昌幸と共に石田三成に従い、犬伏にて徳川家康に従った信之を別れました。その後、第2次上田城の戦いでは徳川秀忠率いる徳川本隊を釘付けにして関ヶ原の戦いに遅参させる成果を上げる。
しかし裏切りなどもあって石田三成が関ヶ原の戦い敗戦すると、父共々降伏した。家康は当初、昌幸・幸村を死罪にするつもりであったが兄・信之をはじめ信之の義父・本多忠勝、井伊直政の必死の除名嘆願もあって命だけは助けられるが九度山に幽閉される。
14年の幽閉生活のあとに九度山を抜けだし大阪の陣に参戦。冬の陣にて真田丸を築き徳川勢を迎え撃った。しかし和平交渉の後、外堀内堀を埋められ真田丸も取り壊された状態で夏の陣に突入。
夏の陣では修羅の如く徳川本隊に突撃し、三方原の戦い以来2度目となる家康の馬印を倒す成果を上げ、家康を切腹寸前まで追い詰めるがあと一歩及ばずに戦死した。
1568年(永禄11年)
| 毛利元就 | 71歳 |
| 北条氏康 | 53歳 |
| 武田信玄 | 47歳 |
| 明智光秀 | 40歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 38歳 |
| 小早川隆景 | 35歳 |
| 織田信長 | 34歳 |
| 島津義弘 | 33歳 |
| 佐々成政 | 32歳 |
| 豊臣秀吉 | 31歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 30歳 |
| 長宗我部元親 | 29歳 |
| 徳川家康 | 25歳 |
| 竹中半兵衛 | 24歳 |
| 山内一豊 | 23歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 22歳 |
| 真田昌幸 | 21歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 20歳 |
| 毛利輝元 | 15歳 |
| 織田信忠 | 11歳 |
| 直江兼続 | 9歳 |
| 石田三成 | 8歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 7歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 6歳 |
| 真田信之 | 2歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 1歳 |
黒田長政誕生
天才軍師と言われた黒田官兵衛の長男として誕生。
秀吉死後に起きた関ヶ原の戦いでは徳川家康側につき東軍として活躍。
父である官兵衛は長政を猪武者といっていたが、関ヶ原の戦いでは寝返りを交渉を請け負っており父譲りの調略で西軍の小早川秀秋や吉川広家を寝返えらせ東軍勝利の貢献した。
戦後は先ほどの活躍から子々孫々まで罪を免除するお墨付きをもらったばかりか、筑前国約52万石を拝領して福岡藩を設立させ初代藩主となり現在の福岡県の礎を築いた。
1571年(元亀2年)
| 毛利元就 | 死去(74歳) |
| 北条氏康 | 死去(56歳) |
| 武田信玄 | 50歳 |
| 明智光秀 | 43歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 41歳 |
| 小早川隆景 | 38歳 |
| 織田信長 | 37歳 |
| 島津義弘 | 36歳 |
| 佐々成政 | 35歳 |
| 豊臣秀吉 | 34歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 33歳 |
| 長宗我部元親 | 32歳 |
| 徳川家康 | 28歳 |
| 竹中半兵衛 | 27歳 |
| 山内一豊 | 26歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 25歳 |
| 真田昌幸 | 24歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 23歳 |
| 毛利輝元 | 18歳 |
| 織田信忠 | 14歳 |
| 直江兼続 | 12歳 |
| 石田三成 | 11歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 10歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 9歳 |
| 真田信之 | 5歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 4歳 |
毛利元就死去
1代で毛利家を中国地方最大の戦国大名に成長させた毛利元就が毛利家の居城・吉田郡山城で死去。
死因は胃癌とも老衰とも言われています。
元就の死去に伴って、輝元との二頭政治は終了し、叔父の吉川元春・小早川隆景の補佐を受けながら輝元の親政が開始された。
北条氏康死去
30年以上も北条家を率いた北条氏康が1571年(元亀2年)に北条家の居城・小田原城で死去。
死因は中風(現代でいう脳卒中)。記録によれば病床時は武田信玄が侵攻したことも理解できなかったそうです。
1573年(元亀4年)
| 武田信玄 | 死去(52歳) |
| 明智光秀 | 45歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 43歳 |
| 小早川隆景 | 40歳 |
| 織田信長 | 39歳 |
| 島津義弘 | 38歳 |
| 佐々成政 | 37歳 |
| 豊臣秀吉 | 36歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 35歳 |
| 長宗我部元親 | 34歳 |
| 徳川家康 | 30歳 |
| 竹中半兵衛 | 29歳 |
| 山内一豊 | 28歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 27歳 |
| 真田昌幸 | 26歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 25歳 |
| 毛利輝元 | 20歳 |
| 織田信忠 | 16歳 |
| 直江兼続 | 14歳 |
| 石田三成 | 13歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 12歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 11歳 |
| 真田信之 | 7歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 6歳 |
| 黒田長政 | 5歳 |
宇喜多秀家誕生
豊臣家・五大老の1人で宇喜多家当主となった幼少時から秀吉に重用された戦国武将。
秀吉死後は西軍として石田三成に与するも小早川秀秋の裏切りで大谷軍は壊滅、宇喜多軍は壊滅し西軍は徳川家康率いる東軍に敗北する。
宇喜多家は改易されるが、秀家は落ち武者狩りをその度にくぐり抜けて1655年(明暦元年)11月20日に84歳で死去した。
この時既に徳川幕府4代将軍・徳川家綱時代であったとされ、謝罪や助命嘆願で改易を免れたりした西軍の中心的武将の中では唯一逃げ切りに成功した人物でもあります。
三方ヶ原の戦い
武田信玄と織田信長・徳川家康連合との間で起こった戦い。
武田信玄は信長包囲網に参加すべく西上作戦を展開し上洛を目指すために西へ侵攻。
その過程で三河を拠点としていた徳川家康と激突した。この戦いで武田信玄は徳川家康に勝利した。
家康は九死に一生を得て命からがら浜松城へと敗走した。
武田信玄死去
三方ヶ原の戦いで家康を敗退させた武田信玄はその勢いで西に侵攻するも、持病が悪化し侵攻が停止。
陣中で療養するも回復が見込まれないために武田軍は甲斐に撤退を決意する。
しかしその撤退の最中、陣中で死去。死因は食道がんとも胃がんとも日本住血吸虫症とも言われています。
信玄死去に伴って武田家の西上作戦は頓挫。包囲網が機能しなくなったことで信長は危機を脱しました。
1575年(天正3年)
| 明智光秀 | 47歳 |
| 上杉謙信 | 45歳 |
| 吉川元春 | 45歳 |
| 小早川隆景 | 42歳 |
| 織田信長 | 41歳 |
| 島津義弘 | 40歳 |
| 佐々成政 | 39歳 |
| 豊臣秀吉 | 38歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 37歳 |
| 長宗我部元親 | 36歳 |
| 徳川家康 | 32歳 |
| 竹中半兵衛 | 31歳 |
| 山内一豊 | 30歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 29歳 |
| 真田昌幸 | 28歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 27歳 |
| 毛利輝元 | 22歳 |
| 織田信忠 | 18歳 |
| 直江兼続 | 16歳 |
| 石田三成 | 15歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 14歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 13歳 |
| 真田信之 | 9歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 8歳 |
| 黒田長政 | 7歳 |
| 宇喜田秀家 | 2歳 |
長篠の戦い
武田信玄の死去から2年後に織田信長・徳川家康の連合軍と武田勝頼との間で起こった戦い。
1575年は織田信長が人類史上はじめて鉄砲を大量を利用した戦でもあります。
当時火縄銃は射程距離が短く1度発砲すると装填して次の発射までに1~2分かかることからあまり重用されていなかった。
しかし信長はこの戦いで鉄砲隊を3隊列編成にして撃ったら次の列に変わって撃ち続けるという連射戦術を用いることで火縄銃の弱点克服・火力を最大限活用し当時最強と言われた武田軍を打ち破り勝利しました。
この戦いで武田家は馬場信春をはじめ、真田信綱・昌輝など信玄時代からの仕えてきた子飼いの重臣たちの多くが戦死し大敗。
武田家の衰退と織田家の更なる勢力拡大の分水嶺になりました。
1576年(天正4年)
| 明智光秀 | 48歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 46歳 |
| 小早川隆景 | 43歳 |
| 織田信長 | 42歳 |
| 島津義弘 | 41歳 |
| 佐々成政 | 40歳 |
| 豊臣秀吉 | 39歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 38歳 |
| 長宗我部元親 | 37歳 |
| 徳川家康 | 33歳 |
| 竹中半兵衛 | 32歳 |
| 山内一豊 | 31歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 30歳 |
| 真田昌幸 | 29歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 28歳 |
| 毛利輝元 | 23歳 |
| 織田信忠 | 19歳 |
| 直江兼続 | 17歳 |
| 石田三成 | 16歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 15歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 14歳 |
| 真田信之 | 10歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 9歳 |
| 黒田長政 | 8歳 |
| 宇喜田秀家 | 3歳 |
第一次木津川口の戦い
石山本願寺より救援要請を受けた毛利輝元とそれを阻止しようとする織田信長との間で起こった戦い。
実質的には毛利・小早川・村上水軍といった瀬戸内水軍と織田水軍の戦いで結果は毛利方の水軍が勝利した。
毛利方の水軍は焙烙玉・火矢などを用いて織田水軍を攻め、織田方の水軍は壊滅的な打撃を受けて敗走しました。
1577年(天正5年)
| 明智光秀 | 49歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 47歳 |
| 小早川隆景 | 44歳 |
| 織田信長 | 43歳 |
| 島津義弘 | 42歳 |
| 佐々成政 | 41歳 |
| 豊臣秀吉 | 40歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 39歳 |
| 長宗我部元親 | 38歳 |
| 徳川家康 | 34歳 |
| 竹中半兵衛 | 33歳 |
| 山内一豊 | 32歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 31歳 |
| 真田昌幸 | 30歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 29歳 |
| 毛利輝元 | 24歳 |
| 織田信忠 | 20歳 |
| 直江兼続 | 18歳 |
| 石田三成 | 17歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 16歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 15歳 |
| 真田信之 | 11歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 10歳 |
| 黒田長政 | 9歳 |
| 宇喜田秀家 | 4歳 |
手取川の戦い
越後を攻略したい織田信長と上杉謙信との間で起こった戦い。
この時信長は出陣しておらず、柴田勝家を総大将として北国に進軍していた。
しかし無類の強さを誇る上杉謙信は織田軍を撃破・敗走させ上杉家の居城・春日山城へ凱旋。帰還後するに次の遠征に向けての大動員令を発布した。
1578年(天正6年)
| 明智光秀 | 50歳 |
| 上杉謙信 | 死去(48歳) |
| 吉川元春 | 48歳 |
| 小早川隆景 | 45歳 |
| 織田信長 | 44歳 |
| 島津義弘 | 43歳 |
| 佐々成政 | 42歳 |
| 豊臣秀吉 | 41歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 40歳 |
| 長宗我部元親 | 39歳 |
| 徳川家康 | 35歳 |
| 竹中半兵衛 | 34歳 |
| 山内一豊 | 33歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 32歳 |
| 真田昌幸 | 31歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 30歳 |
| 毛利輝元 | 25歳 |
| 織田信忠 | 21歳 |
| 直江兼続 | 19歳 |
| 石田三成 | 18歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 17歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 16歳 |
| 真田信之 | 12歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 11歳 |
| 黒田長政 | 10歳 |
| 宇喜田秀家 | 5歳 |
上杉謙信死去
手取川の戦いで勝利した上杉謙信は1577年(天正5年)に大動員令を発布、1578年(天正6年)の春先には出陣予定であった。
しかし遠征準備中かつ出陣6日前に倒れて急死。死因は脳溢血と言われています。
信玄に続いて謙信という強大なライバルが消えたことで、織田信長は天下統一に向けてより邁進していくことになります。
第二次木津川口の戦い
織田信長と毛利輝元との間で行われた戦い。この戦いも第一次木津川口の戦い同様に毛利家が石山本願寺より救援要請を受けたことが発端。
第一次木津川口の戦いでは勝利した毛利方だったがこの戦いでは九鬼嘉隆率いる織田水軍が大筒などを装備し焙烙玉・火矢が効かない鉄甲船6隻を用いたことで織田水軍が勝利した。
救援物資を石山本願寺に届けたために毛利軍の目的は達成したが、制海権を織田家に奪われたことで徐々に織田軍に圧倒されていくことになります。
1579年(天正7年)
| 明智光秀 | 51歳 |
| 吉川元春 | 49歳 |
| 小早川隆景 | 46歳 |
| 織田信長 | 45歳 |
| 島津義弘 | 44歳 |
| 佐々成政 | 43歳 |
| 豊臣秀吉 | 42歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 41歳 |
| 長宗我部元親 | 40歳 |
| 徳川家康 | 36歳 |
| 竹中半兵衛 | 死去(35歳) |
| 山内一豊 | 34歳 |
| 武田勝頼・黒田官兵衛 | 33歳 |
| 真田昌幸 | 32歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 31歳 |
| 毛利輝元 | 26歳 |
| 織田信忠 | 22歳 |
| 直江兼続 | 20歳 |
| 石田三成 | 19歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 18歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 17歳 |
| 真田信之 | 13歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 12歳 |
| 黒田長政 | 11歳 |
| 宇喜田秀家 | 6歳 |
| 小早川秀秋 | 2歳 |
徳川秀忠誕生
徳川家康の三男として誕生。
三男であり本来徳川家の後継者の地位ではなかったが、家康の長男・信康は謀反の疑いをかけられ信長の命で切腹、次男・秀康は豊臣家に養子に出されて結城家を継いだことから跡取り候補となる。
関ヶ原の戦いでは徳川本隊を率いる。
しかし真田昌幸・幸村親子に上田城で足止めを食らい、長雨によって家康の命令書の到着遅れ・進軍の遅れで徳川本隊が関ヶ原の戦いに遅参するという大失態を起こしてしまう。
しかし本多正信や榊原康政の尽力もあって、家康に許しをもらい1605年に家康の跡を継いで江戸幕府2代将軍となった。
初代将軍の家康や3代将軍の息子・家光と比べると知名度は低いが、家康の跡を継いで江戸幕府の支配を完全に確立・江戸の町づくりを行うなど礎を築きました。
竹中半兵衛死去
豊臣秀吉が中国攻めの一環として播磨征伐・三木合戦を行っていた陣中で死去。
死因は肺結核と言われています。
当時黒田官兵衛は有岡城の荒木村重に幽閉されており、信長はそれを裏切りだと勘違いし人質だった官兵衛の長男・長政を殺すように命令しました。
しかし半兵衛は官兵衛は裏切っていないと信じており、長政を匿い長政を助けたそうです。
半兵衛の死後、有岡城攻略の際に官兵衛は疑いが晴れ、長政は官兵衛の元に戻ることができました。
半兵衛は死して尚、信長を欺いただけでなく、秀吉が天下統一をする礎を築いたといって良いでしょう。
1582年(天正10年)
この1582年(天正10年)は武田家滅亡・本能寺の変・明智光秀の三日天下など様々な事象が発生し、多くの有力武将が死亡、全国の勢力図が一変することとなりました。
| 明智光秀 | 死去(54歳) |
| 吉川元春 | 52歳 |
| 小早川隆景 | 49歳 |
| 織田信長 | 死去(48歳) |
| 島津義弘 | 47歳 |
| 佐々成政 | 46歳 |
| 豊臣秀吉 | 45歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 44歳 |
| 長宗我部元親 | 43歳 |
| 徳川家康 | 39歳 |
| 山内一豊 | 37歳 |
| 武田勝頼 | 死去(36歳) |
| 黒田官兵衛 | 36歳 |
| 真田昌幸 | 35歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 34歳 |
| 毛利輝元 | 29歳 |
| 織田信忠 | 死去(25歳) |
| 直江兼続 | 23歳 |
| 石田三成 | 22歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 21歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 20歳 |
| 真田信之 | 16歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 15歳 |
| 黒田長政 | 14歳 |
| 宇喜田秀家 | 9歳 |
| 徳川秀忠 | 3歳 |
小早川秀秋誕生
豊臣秀吉の正室である北政所の甥として誕生し、親戚であったことから豊臣親族として活躍していた。
秀吉の命で子のいなかった毛利元就の三男・小早川隆景の養子となり、小早川秀秋と名乗るようになる。
関ヶ原の戦いでは西軍でありながら黒田長政と通じており、戦いも佳境に差し掛かった時に西軍を裏切り、大谷吉継次いで宇喜多秀家を攻撃し徳川家康率いる東軍の勝利に貢献し豊臣家衰退のきっかけをつくった。
戦後は宇喜多秀家の旧領であった備後・岡山城主となるが、関ヶ原の戦いからわずか2年後の1602年に20歳という若さで死去した。
甲州征伐
武田信玄の死後から9年、長篠の戦いから7年後の1582年(天正10年)に起きた武田勝頼と織田信長の間で起きた戦い。
織田方は武田方の武将を次々と調略し、武田家一門筆頭の穴山梅雪や木曾義昌らが相次いで織田方へ離反。
結果、家臣団はバラバラとなり、天目山の戦いで武田勝頼は織田軍に追い詰められて自刃し死去。
この結果、戦国最強と言われた名門・甲斐の武田家は滅亡しました。
備中高松城の戦い
中国攻めを任された織田方の豊臣秀吉と毛利輝元の間で起きた戦い。
この戦いで秀吉は清水宗治が守る備中高松城を水攻めにして孤立する作戦を敢行。
この結果、毛利軍は容易に備中高松城を救援できなくなり、秀吉有利で戦局は硬直、毛利は和睦交渉へと戦略を転換せざる負えない状況になりました。
この戦いの最中、京都で本能寺の変が勃発します。
本能寺の変勃発
織田家の家臣・明智光秀が京都の本能寺で宿泊していた織田信長を突如裏切って急襲した事件。
この結果、天下統一目前だった織田信長が死去、信長の長男・信忠も死去し、織田家は衰退していきます。
豊臣秀吉が中国大返しを敢行
備中高松城で水攻めを行っていた秀吉だったが信長の訃報を知るや、黒田官兵衛の力を借り速やかに毛利軍と和睦。
一気に馬首を返して主君・信長の敵討ちをするべく畿内へとUターンをはじめた。
結果的に本能寺の変から11日後という当時の道路や移動技術としては驚異的な速さで明智光秀と山崎で対峙することとなります。
山崎の戦い
豊臣秀吉と明智光秀の間で起こった戦い。
秀吉は本能寺の変からわずか11日で中国地方から畿内へと舞い戻り、光秀と激突しました。
結果的に秀吉は光秀に勝利。光秀は敗走途中に落武者狩りにあって死去。
これにより秀吉は信長の後継者として世間に認知されていくことになります。
ちなみに本能寺の変が起きた1582年(天正10年)時点でのそれぞれの年齢は明智光秀は54歳、織田信長は48歳、豊臣秀吉は45歳、徳川家康は39歳でした。
1584年(天正12年)
| 吉川元春 | 54歳 |
| 小早川隆景 | 51歳 |
| 島津義弘 | 49歳 |
| 佐々成政 | 48歳 |
| 豊臣秀吉 | 47歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 46歳 |
| 長宗我部元親 | 45歳 |
| 徳川家康 | 41歳 |
| 山内一豊 | 39歳 |
| 黒田官兵衛 | 38歳 |
| 真田昌幸 | 37歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 36歳 |
| 毛利輝元 | 31歳 |
| 直江兼続 | 25歳 |
| 石田三成 | 24歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 23歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 22歳 |
| 真田信之 | 18歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 17歳 |
| 黒田長政 | 16歳 |
| 宇喜田秀家 | 11歳 |
| 徳川秀忠 | 5歳 |
| 小早川秀秋 | 2歳 |
小牧・長久手の戦い
信長の地位を確立した豊臣秀吉は織田信長の3男・織田信雄に侵攻、その結果信雄より援軍要請を受けた徳川家康が参戦。これにより秀吉軍VS信雄・家康連合軍という図式で小牧・長久手の戦いが勃発しました。
結果は信雄が秀吉と停戦したため引き分けとなりましたが、家康は局地戦とはいえ秀吉に勝利。
本能寺の変後に天下統一を推し進める秀吉にとって後にも先にも負けたのはこの戦いだけであり、家康は唯一秀吉に勝利した相手ということになります。
家康の力を再認識した秀吉は力推しでは駄目だと判断し、以降は外交政策で家康を傘下に取り込もうとしたそうです。
1585年(天正13年)
| 吉川元春 | 55歳 |
| 小早川隆景 | 52歳 |
| 島津義弘 | 50歳 |
| 佐々成政 | 49歳 |
| 豊臣秀吉 | 48歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 47歳 |
| 長宗我部元親 | 46歳 |
| 徳川家康 | 42歳 |
| 山内一豊 | 40歳 |
| 黒田官兵衛 | 39歳 |
| 真田昌幸 | 38歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 37歳 |
| 毛利輝元 | 32歳 |
| 直江兼続 | 26歳 |
| 石田三成 | 25歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 24歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 23歳 |
| 真田信之 | 19歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 18歳 |
| 黒田長政 | 17歳 |
| 宇喜田秀家 | 12歳 |
| 徳川秀忠 | 6歳 |
| 小早川秀秋 | 3歳 |
四国征伐
信長の死後、いち早く裏切り者であった明智光秀を討ち後継者となった秀吉は賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を倒し畿内の安定に成功。
その勢いで四国に侵攻し長宗我部家に勝利。
四国を平定し天下統一に向けてさらに邁進していくことになります。
1586年(天正14年)
| 吉川元春 | 死去(56歳) |
| 小早川隆景 | 53歳 |
| 島津義弘 | 51歳 |
| 佐々成政 | 50歳 |
| 豊臣秀吉 | 49歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 48歳 |
| 長宗我部元親 | 47歳 |
| 徳川家康 | 43歳 |
| 山内一豊 | 41歳 |
| 黒田官兵衛 | 40歳 |
| 真田昌幸 | 39歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 38歳 |
| 毛利輝元 | 33歳 |
| 直江兼続 | 27歳 |
| 石田三成 | 26歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 25歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 24歳 |
| 真田信之 | 20歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 19歳 |
| 黒田長政 | 18歳 |
| 宇喜田秀家 | 13歳 |
| 徳川秀忠 | 7歳 |
| 小早川秀秋 | 4歳 |
吉川元春死去
豊臣秀吉の要請で九州征伐に従軍していた毛利元就の次男・吉川元春が遠征先の豊前小倉城の陣中で死去。
死因は化膿性炎症、癌とも言われています。
元春の死後、後を追うように吉川家当主で元春の長男・吉川元長も死去。元長の死去により吉川広家が吉川家当主となりました。
1587年(天正15年)
| 小早川隆景 | 54歳 |
| 島津義弘 | 52歳 |
| 佐々成政 | 51歳 |
| 豊臣秀吉 | 50歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 49歳 |
| 長宗我部元親 | 48歳 |
| 徳川家康 | 44歳 |
| 山内一豊 | 42歳 |
| 黒田官兵衛 | 41歳 |
| 真田昌幸 | 40歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 39歳 |
| 毛利輝元 | 34歳 |
| 直江兼続 | 28歳 |
| 石田三成 | 27歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 26歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 25歳 |
| 真田信之 | 21歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 20歳 |
| 黒田長政 | 19歳 |
| 宇喜田秀家 | 14歳 |
| 小早川秀秋 | 10歳 |
| 徳川秀忠 | 8歳 |
| 小早川秀秋 | 5歳 |
九州征伐終結
発端は島津家に侵攻された大友家が豊臣秀吉に援軍を要請したことから始まる。
九州に援軍を送ろうとしていた当初は徳川家康が秀吉の軍門に下っておらず西と東から挟撃されると進退が危うくなることから自ら出陣出来なかった。
そのため黒田家や毛利家を先発隊として派遣。黒田官兵衛ら黒田軍と毛利輝元・小早川隆景・吉川元春といった毛利主力軍が九州にて活躍しました。
その間に秀吉は実母を人質に出すことで遂に家康を屈服させ東の懸念を無くすことに成功。
秀吉は豊臣本隊を率いて高らかに九州に侵攻し島津家に勝利。1586年から続いた九州征伐は1587年に集結し秀吉は九州を平定しました。
この結果により秀吉の敵は関東の北条家、東北の伊達政宗のみとなりました。
1588年(天正16年)
| 小早川隆景 | 55歳 |
| 島津義弘 | 53歳 |
| 佐々成政 | 死去(52歳) |
| 豊臣秀吉 | 51歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 50歳 |
| 長宗我部元親 | 49歳 |
| 徳川家康 | 45歳 |
| 山内一豊 | 43歳 |
| 黒田官兵衛 | 42歳 |
| 真田昌幸 | 41歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 40歳 |
| 毛利輝元 | 35歳 |
| 直江兼続 | 29歳 |
| 石田三成 | 28歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 27歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 26歳 |
| 真田信之 | 22歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 21歳 |
| 黒田長政 | 20歳 |
| 宇喜田秀家 | 15歳 |
| 徳川秀忠 | 9歳 |
| 小早川秀秋 | 6歳 |
佐々成政死去
九州征伐の功が認められ肥後一国を与えられた佐々成政だったが領内で一揆が勃発。
その責任を負わされ切腹し死去しました。
切腹後、肥後には加藤清正が入国し統治していくことになります。
1590年(天正18年)
| 小早川隆景 | 57歳 |
| 島津義弘 | 55歳 |
| 豊臣秀吉 | 53歳 |
| 北条氏政 | 小田原城の戦いにて敗戦し切腹(52歳) |
| 前田利家・本多正信 | 52歳 |
| 長宗我部元親 | 51歳 |
| 徳川家康 | 47歳 |
| 山内一豊 | 45歳 |
| 黒田官兵衛 | 44歳 |
| 真田昌幸 | 43歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 42歳 |
| 毛利輝元 | 37歳 |
| 直江兼続 | 31歳 |
| 石田三成 | 30歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 29歳 |
| 北条氏直・加藤清正 | 28歳 |
| 真田信之 | 24歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 23歳 |
| 黒田長政 | 22歳 |
| 宇喜田秀家 | 17歳 |
| 小早川秀秋 | 13歳 |
| 徳川秀忠 | 11歳 |
| 小早川秀秋 | 8歳 |
小田原城の戦い
北条氏政・氏直父子率いる北条家と豊臣秀吉の間で起こった戦い。
北条家は豊臣秀吉の天下惣無事令を無視し、真田領内など近隣国に侵攻。
秀吉は再三に渡って使者を送り、上洛・臣従するように説得するも応じない北条家へ相手についに出兵。
戦国時代史上最大規模の動員数を誇る20万の大軍を率いて小田原に侵攻し、八王子城など小田原城周辺の北条家の支城を次々と攻略し小田原城を包囲。
この戦いで伊達政宗は秀吉の軍門に下り、家康も天下統一の夢をしばらく封印。この結果、孤立無援となった北条家は降伏。
北条家4代目当主・北条氏政は戦の責任を取り切腹、5代目当主・氏直は出家し高野山に追放され戦国大名・北条家は滅亡しました。
豊臣秀吉が天下統一
小田原城の戦いで北条家を滅亡させ、伊達政宗を軍門に加えた秀吉は三河・遠江一円を支配していた家康を関東に移封させ封じ込めに成功。
応仁の乱より約120年間続いた戦国時代を織田信長の後継者として旧領を受け継いでから僅か約8年で終焉させました。
1591年(天正19年)
| 小早川隆景 | 58歳 |
| 島津義弘 | 56歳 |
| 豊臣秀吉 | 54歳 |
| 前田利家・本多正信 | 53歳 |
| 長宗我部元親 | 52歳 |
| 徳川家康 | 48歳 |
| 山内一豊 | 46歳 |
| 黒田官兵衛 | 45歳 |
| 真田昌幸 | 44歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 43歳 |
| 毛利輝元 | 38歳 |
| 直江兼続 | 32歳 |
| 石田三成 | 31歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 30歳 |
| 北条氏直 | 死去(29歳) |
| 加藤清正 | 29歳 |
| 真田信之 | 25歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 24歳 |
| 黒田長政 | 23歳 |
| 宇喜田秀家 | 18歳 |
| 徳川秀忠 | 12歳 |
| 小早川秀秋 | 9歳 |
北条氏直死去
北条家が滅亡し高野山へ追放された氏直だったが赦免活動の末に赦免を勝ち取り、豊臣大名として復活することができた。
しかし天然痘を患い、29歳の若さで心半ばに死去した。
1593年(文禄2年)
| 小早川隆景 | 60歳 |
| 島津義弘 | 58歳 |
| 豊臣秀吉 | 56歳 |
| 前田利家・本多正信 | 55歳 |
| 長宗我部元親 | 54歳 |
| 徳川家康 | 50歳 |
| 山内一豊 | 48歳 |
| 黒田官兵衛 | 47歳 |
| 真田昌幸 | 46歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 45歳 |
| 毛利輝元 | 40歳 |
| 直江兼続 | 34歳 |
| 石田三成 | 33歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 32歳 |
| 加藤清正 | 31歳 |
| 真田信之 | 27歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 26歳 |
| 黒田長政 | 25歳 |
| 宇喜田秀家 | 20歳 |
| 小早川秀秋 | 16歳 |
| 徳川秀忠 | 14歳 |
| 小早川秀秋 | 11歳 |
豊臣秀頼誕生
豊臣秀吉の次男として誕生。母は淀殿。長男は既に早世していたために豊臣家の後継者となる。
長男が早世し嘆き悲しんでいた秀吉にとって誕生した世継ぎであってとても溺愛していたが、その秀吉は秀頼の将来を案じながら1598年秀頼が5歳の時に死去。
秀吉の死後、秀頼の後見として前田利家を指名するも利家も死去。その後関ヶ原の戦いにて石田三成ら豊臣恩顧の大名は死去か家康に臣従したことで豊臣家は衰退。
その後は一定の勢力は保っていたが、1614年の大阪冬の陣・1615年の大阪夏の陣にて徳川家に攻められて自刃。秀頼の自刃に伴って豊臣家は滅亡した。
1597年(慶長2年)
| 小早川隆景 | 死去(64歳) |
| 島津義弘 | 62歳 |
| 豊臣秀吉 | 60歳 |
| 前田利家・本多正信 | 59歳 |
| 長宗我部元親 | 58歳 |
| 徳川家康 | 54歳 |
| 山内一豊 | 52歳 |
| 黒田官兵衛 | 51歳 |
| 真田昌幸 | 50歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 49歳 |
| 毛利輝元 | 44歳 |
| 直江兼続 | 38歳 |
| 石田三成 | 37歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 36歳 |
| 加藤清正 | 35歳 |
| 真田信之 | 31歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 30歳 |
| 黒田長政 | 29歳 |
| 宇喜田秀家 | 24歳 |
| 徳川秀忠 | 18歳 |
| 小早川秀秋 | 15歳 |
| 豊臣秀頼 | 4歳 |
小早川隆景死去
毛利元就の三男で兄・吉川元春の死去後は毛利両川の最後の1人して毛利家を支えていた小早川隆景が居城・三原城で死去した。
訃報に際して、黒田官兵衛は「これでこの国に賢人はいなくなった」と嘆いたと言われています。
隆景死去後、養子の小早川秀秋に臣従したくない譜代家臣は毛利本家に帰参し、小早川家は秀吉から派遣された家臣団が補佐。
この結果、毛利両川体制は吉川元春の三男で吉川家当主の吉川広家、元就の四男・穂井田元清の次男・毛利秀元が受け継ぎ毛利家を補佐していくことになります。
1598年(慶長3年)
| 島津義弘 | 63歳 |
| 豊臣秀吉 | 死去(61歳) |
| 前田利家 | 60歳 |
| 本多正信 | 60歳 |
| 長宗我部元親 | 59歳 |
| 徳川家康 | 55歳 |
| 山内一豊 | 53歳 |
| 黒田官兵衛 | 52歳 |
| 真田昌幸 | 51歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 50歳 |
| 毛利輝元 | 45歳 |
| 直江兼続 | 39歳 |
| 石田三成 | 38歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 37歳 |
| 加藤清正 | 36歳 |
| 真田信之 | 32歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 31歳 |
| 黒田長政 | 30歳 |
| 宇喜田秀家 | 25歳 |
| 徳川秀忠 | 19歳 |
| 小早川秀秋 | 16歳 |
| 豊臣秀頼 | 5歳 |
豊臣秀吉死去
本能寺の変にて織田信長の横死後、頭角を現わし信長の地位と基盤を受け継ぎ天下人とて天下統一事業を達成した豊臣秀吉。
そのカリスマ性と天性の人たらしの力を存分に発揮し一癖も二癖もある各地の武将たちをまとめた彼も寄る年波を超えることはできず僅か5歳の子・豊臣秀頼の将来を案じながら大阪城で死去。
死因は下痢や腹痛をはじめ大腸がんや赤痢など様々ではっきりとしたことは分かっていません。
秀吉のカリスマ性で統率されていた家臣団は彼の死後、福島正則・加藤清正といった武断派と石田三成ら文治派の対立激化によって崩壊をはじめ、関ヶ原の戦い以降は家康の台頭を許し豊臣家は急速に衰退していくことになります。
1599年(慶長4年)
| 島津義弘 | 63歳 |
| 前田利家 | 死去(61歳) |
| 本多正信 | 61歳 |
| 長宗我部元親 | 死去(60歳) |
| 徳川家康 | 56歳 |
| 山内一豊 | 54歳 |
| 黒田官兵衛 | 53歳 |
| 真田昌幸 | 52歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 51歳 |
| 毛利輝元 | 46歳 |
| 直江兼続 | 40歳 |
| 石田三成 | 39歳 |
| 井伊直政・福島正則 | 38歳 |
| 加藤清正 | 37歳 |
| 真田信之 | 33歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 32歳 |
| 黒田長政 | 31歳 |
| 宇喜田秀家 | 26歳 |
| 徳川秀忠 | 20歳 |
| 小早川秀秋 | 17歳 |
| 豊臣秀頼 | 6歳 |
前田利家死去
豊臣秀吉の死後、その子供・秀頼の傅役として大坂城の実質的主として勤めていた五大老の1人・前田利家が死去。
死因は内蔵系のがんだそうです。
前田利家が亡くなるということは福島正則などの武断派と石田三成などの文治派の仲介役がいなくなるということを意味しており、彼の死後、豊臣家臣団は分裂し徳川家康が台頭。
豊臣家が衰退するきっかけとなる関ヶ原の戦いへ突き進むことになります。
長宗我部元親死去
四国の雄・長宗我部元親が死去。
死因は病死と言われている。
彼の死後、長宗我部家は関ヶ原の戦い後に改易され旧領の土佐は山内一豊が統治していくことになります。
1600年(慶長5年)
| 島津義弘 | 65歳 |
| 本多正信 | 62歳 |
| 徳川家康 | 57歳 |
| 山内一豊 | 55歳 |
| 黒田官兵衛 | 54歳 |
| 真田昌幸 | 53歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 52歳 |
| 毛利輝元 | 47歳 |
| 直江兼続 | 41歳 |
| 石田三成 | 死去(40歳) |
| 井伊直政 | 39歳 |
| 福島正則 | 39歳 |
| 加藤清正 | 38歳 |
| 真田信之 | 34歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 33歳 |
| 黒田長政 | 32歳 |
| 宇喜田秀家 | 27歳 |
| 徳川秀忠 | 21歳 |
| 小早川秀秋 | 18歳 |
| 豊臣秀頼 | 7歳 |
関ヶ原の戦い
石田三成と徳川家康の間で起きた戦い。上杉征伐のために徳川家康が諸大名を集めて出陣したのが発端。
家康が大阪を空けた機会に乗じて石田三成が挙兵。大阪城を掌握して上杉家と挟撃すべく進軍しました。
しかし家康は福島正則や加藤清正など豊臣恩顧の大名を味方に引き込みこれを察して石田光成を迎え撃つべく大阪へ転進し両軍は関ヶ原で激闘しました。
当時の情勢は徳川秀忠率いる本隊が上田城で足止めをくらったことと長雨で遅参したことが仇となり、三成率いる西軍が有利でした。
しかし家康が戦場を得意の野戦に持ち込んだこと、小早川秀秋をはじめとした西軍に与していた諸将の裏切りもあって三成率いる西軍を撃破し家康は勝利しました。
この結果、大谷吉継をはじめ多くの武将が戦死し、石田三成も捕縛・斬首され死去。
この戦いは結果的に豊臣家の衰退と徳川家へ支配体制移行する分水嶺となりました。
1602年(慶長7年)
| 島津義弘 | 67歳 |
| 本多正信 | 64歳 |
| 徳川家康 | 59歳 |
| 山内一豊 | 57歳 |
| 黒田官兵衛 | 56歳 |
| 真田昌幸 | 55歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 54歳 |
| 毛利輝元 | 49歳 |
| 直江兼続 | 43歳 |
| 井伊直政 | 死去(41歳) |
| 福島正則 | 41歳 |
| 加藤清正 | 40歳 |
| 真田信之 | 36歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 35歳 |
| 黒田長政 | 34歳 |
| 宇喜田秀家 | 29歳 |
| 徳川秀忠 | 23歳 |
| 小早川秀秋 | 死去(20歳) |
| 豊臣秀頼 | 9歳 |
井伊直政死去
若いながら徳川四天王の1人に数えられた井伊直政が死去。
死因は関ヶ原の戦いで受けた鉄砲傷(銃創)と言われてます。
直政の死後、彦根藩は明治時代まで井伊家の藩として存続。
彦根藩は西国の抑えと非常時の朝廷の守護を任されていたことからいかに直政が家康に信頼されていたかが分かります。
小早川秀秋死去
関ヶ原の戦いで裏切り者のそしりを受けていた小早川秀秋が20歳という若さで死去。
死因はアルコール依存症による内臓疾患と言われており急死だったそうです。
秀秋の死後、小早川家は断絶し改易されました。
毛利家の願いにより毛利本家から養子を迎えて小早川家が再興されるのはこれから約260年以上後の明治時代になってからのことです。
1603年(慶長8年)
| 島津義弘 | 68歳 |
| 本多正信 | 65歳 |
| 徳川家康 | 60歳 |
| 山内一豊 | 58歳 |
| 黒田官兵衛 | 57歳 |
| 真田昌幸 | 56歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 55歳 |
| 毛利輝元 | 47歳 |
| 直江兼続 | 44歳 |
| 福島正則 | 42歳 |
| 加藤清正 | 41歳 |
| 真田信之 | 37歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 36歳 |
| 黒田長政 | 35歳 |
| 宇喜田秀家 | 30歳 |
| 徳川秀忠 | 24歳 |
| 豊臣秀頼 | 10歳 |
江戸幕府誕生
1600年に石田三成率いる西軍を関ケ原の戦いで破った徳川家康は朝廷より征夷大将軍に任命され江戸に幕府を開きました。
これにより徳川家による天下の統治体制が確立。
ここから260年余りにわたって太平の世を築くことになる江戸幕府がはじまりました。
1604年(慶長9年)
| 島津義弘 | 69歳 |
| 本多正信 | 66歳 |
| 徳川家康 | 61歳 |
| 山内一豊 | 59歳 |
| 黒田官兵衛 | 死去(58歳) |
| 真田昌幸 | 57歳 |
| 榊原康政・本田忠勝 | 56歳 |
| 毛利輝元 | 48歳 |
| 直江兼続 | 45歳 |
| 福島正則 | 43歳 |
| 加藤清正 | 42歳 |
| 真田信之 | 38歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 37歳 |
| 黒田長政 | 36歳 |
| 宇喜田秀家 | 31歳 |
| 徳川秀忠 | 25歳 |
| 豊臣秀頼 | 11歳 |
黒田官兵衛死去
関ヶ原の戦いの4年後に豊臣秀吉を支えた軍師・黒田官兵衛が京都の伏見藩邸で死去。
死因は梅毒と言われていますが詳細は不明だそうで、病死ということになっています。
晩年は中央の政治に一切関与せず、隠居生活を送っていたそうです。
1605年(慶長10年)
| 島津義弘 | 70歳 |
| 本多正信 | 67歳 |
| 徳川家康 | 62歳 |
| 山内一豊 | 死去(60歳) |
| 真田昌幸 | 58歳 |
| 榊原康政 | 57歳 |
| 本田忠勝 | 57歳 |
| 毛利輝元 | 49歳 |
| 直江兼続 | 46歳 |
| 福島正則 | 44歳 |
| 加藤清正 | 43歳 |
| 真田信之 | 39歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 38歳 |
| 黒田長政 | 37歳 |
| 宇喜田秀家 | 32歳 |
| 徳川秀忠 | 26歳 |
| 豊臣秀頼 | 12歳 |
徳川秀忠が征夷大将軍任命され江戸幕府2代将軍に
征夷大将軍として江戸に幕府を開き権勢を奮っていた徳川家康は3男・徳川秀忠に征夷大将軍を譲り江戸幕府の世襲制を確立し世の中に知らしめた。
将軍となった秀忠は江戸にて親政を執り行い幕府支配の基礎固めに着手、家康は大御所として駿府城に拠点を移し自身が死去する1616年まで秀忠との二頭政治を行いました。
山内一豊死去
織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑に仕え、関ヶ原の戦い後は土佐1国20万石を拝領した山内一豊が高知城で病死。
急死という記述だけで具体的な死因は不明。
現在の高知城には一豊の銅像が建てられています。
1606年(慶長11年)
| 島津義弘 | 71歳 |
| 本多正信 | 68歳 |
| 徳川家康 | 63歳 |
| 真田昌幸 | 59歳 |
| 榊原康政 | 死去(58歳) |
| 本田忠勝 | 58歳 |
| 毛利輝元 | 50歳 |
| 直江兼続 | 47歳 |
| 福島正則 | 45歳 |
| 加藤清正 | 44歳 |
| 真田信之 | 40歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 39歳 |
| 黒田長政 | 38歳 |
| 宇喜田秀家 | 33歳 |
| 徳川秀忠 | 27歳 |
| 豊臣秀頼 | 13歳 |
榊原康政死去
本多忠勝と同級生で徳川四天王の1人であった榊原康政が館林で死去。
死因は毛嚢炎と言われている。
康政の功績は大きく康政の死後、榊原家はたびたび改易・断絶の危機を迎えるがその度に「榊原康政の家」というのが影響し、処分されることはなかったと言われています。
1610年(慶長15年)
| 島津義弘 | 75歳 |
| 本多正信 | 72歳 |
| 徳川家康 | 67歳 |
| 真田昌幸 | 63歳 |
| 本田忠勝 | 死去(62歳) |
| 毛利輝元 | 54歳 |
| 直江兼続 | 51歳 |
| 福島正則 | 49歳 |
| 加藤清正 | 48歳 |
| 真田信之 | 44歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 43歳 |
| 黒田長政 | 42歳 |
| 宇喜田秀家 | 37歳 |
| 徳川秀忠 | 31歳 |
| 豊臣秀頼 | 17歳 |
本多忠勝死去
徳川四天王・徳川三傑などに数えられている本田忠勝が桑名で死去。
家康の天下統一を支えた猛将ながら江戸幕府が開かれると病床に伏せることが増えたこと、武闘派よりも文治派が活躍すべきという思いから中枢からは離れました。
しかし中枢を離れたといっても自身が拝領した桑名藩の整備にはまい進し、桑名藩の名君とも言われています。
1611年(慶長16年)
| 島津義弘 | 76歳 |
| 本多正信 | 73歳 |
| 徳川家康 | 68歳 |
| 真田昌幸 | 死去(64歳) |
| 毛利輝元 | 55歳 |
| 直江兼続 | 52歳 |
| 福島正則 | 50歳 |
| 加藤清正 | 死去(49歳) |
| 真田信之 | 45歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 44歳 |
| 黒田長政 | 43歳 |
| 宇喜田秀家 | 38歳 |
| 徳川秀忠 | 32歳 |
| 豊臣秀頼 | 18歳 |
真田昌幸死去
武田信玄子飼いの武将として活躍した真田昌幸が幽閉先の九度山で病死。
関ヶ原の戦い後、助命はされもの九度山に幽閉され10年以上を過ごす。
この間に昌幸は気力を失い、晩年は病気がちだったとも言われています。
これから3年後に起きる大坂冬の陣にはその意思を継いだ次男・幸村が九度山を脱出して参戦し、徳川軍を苦しめることになります。
加藤清正死去
賤ヶ岳の七本槍の1人に数えられ、黒田官兵衛や藤堂高虎に並ぶ築城の名手だった加藤清正が熊本へ戻る船内で急死。
死因は毒殺ともハンセン病だったとも言われています。
関ヶ原の戦いの後、緊迫する豊臣・徳川の仲立ちとなっていた清正の死の影響は大きく、後の大阪の陣に繋がっていきます。
1614年(慶長19年)
| 島津義弘 | 79歳 |
| 本多正信 | 76歳 |
| 徳川家康 | 71歳 |
| 毛利輝元 | 58歳 |
| 直江兼続 | 55歳 |
| 福島正則 | 53歳 |
| 真田信之 | 48歳 |
| 真田幸村・伊達政宗 | 47歳 |
| 黒田長政 | 46歳 |
| 宇喜田秀家 | 41歳 |
| 徳川秀忠 | 35歳 |
| 豊臣秀頼 | 21歳 |
大阪冬の陣
天下をほぼ手中に収めた徳川家康が目の上のたんこぶというべき大阪の豊臣家を滅ぼすべく大阪に侵攻したことで起こった戦い。
全国の大名は家康に臣従しており、加藤清正といった実力のある豊臣恩顧の大名は死去していることから徳川家の圧勝かと思われた。
しかし各地から集まった浪人たちが奮戦。特に真田昌幸の次男・真田幸村が真田丸を築き徳川軍に大打撃を与えた。
また黒田家から出奔していた後藤又兵衛や二度の朝鮮の役で生き残り、関ヶ原の戦いの経験もある毛利勝永などが奮戦し、戦局は硬直状態に突入。
和睦という形で戦は終結した。しかしこの和睦で真田丸は打ち壊され、大阪城の外堀・内堀全てを埋め立てられしまい大阪夏の陣では防御力0で迎え打つこととなりました。
1615年(慶長20年)
| 島津義弘 | 80歳 |
| 本多正信 | 77歳 |
| 徳川家康 | 72歳 |
| 毛利輝元 | 59歳 |
| 直江兼続 | 56歳 |
| 福島正則 | 54歳 |
| 真田信之 | 49歳 |
| 真田幸村 | 死去(48歳) |
| 伊達政宗 | 48歳 |
| 黒田長政 | 47歳 |
| 宇喜田秀家 | 42歳 |
| 徳川秀忠 | 36歳 |
| 豊臣秀頼 | 死去(22歳) |
大阪夏の陣・豊臣家滅亡
応仁の乱以降各地で戦乱が相次いだ戦国時代最後の戦いが徳川家康と豊臣秀頼の間で起きた大阪夏の陣です。
1614年に起きた大阪冬の陣終結に際して大阪城の外堀・内堀とあらゆる堀を埋め立て、南側の出城であった真田丸を打ち壊された。大阪城は丸裸となり豊臣家は劣勢の状態で徳川軍を迎え撃つこととなりました。
しかし予想を反して毛利勝永が奮戦し真田幸村が徳川本陣に突撃。家康は三方ヶ原の戦い以来の屈辱である馬印を倒され自刃一歩まで追い詰められましたが勝利。
豊臣秀頼は大阪城で自刃、真田幸村も四天王寺近くの安居神社で討ち取られ戦死。この戦いで豊臣家を滅亡させ戦国時代に終止符を打ち江戸幕府の支配体制を完全に確立させました。
今日の記事:まとめると意外と楽しいですね
大河ドラマなどでは主人公とその周辺の大名しか登場しませんし、登場しても年齢などは不明瞭ですがこうやってまとめてみると意外に年の差があったりと面白い結果になりました。
1615年の大阪夏の陣では有名な武将のほとんどが死去したか、高齢なのも戦国時代終焉を感じることができます。
別記事ではこの記事の前編として初代戦国武将・北条早雲と戦国時代を終焉させ約260年の太平の世を築いた徳川家康までを現記事同様に年功序列形式でまとめているのでご覧ください。