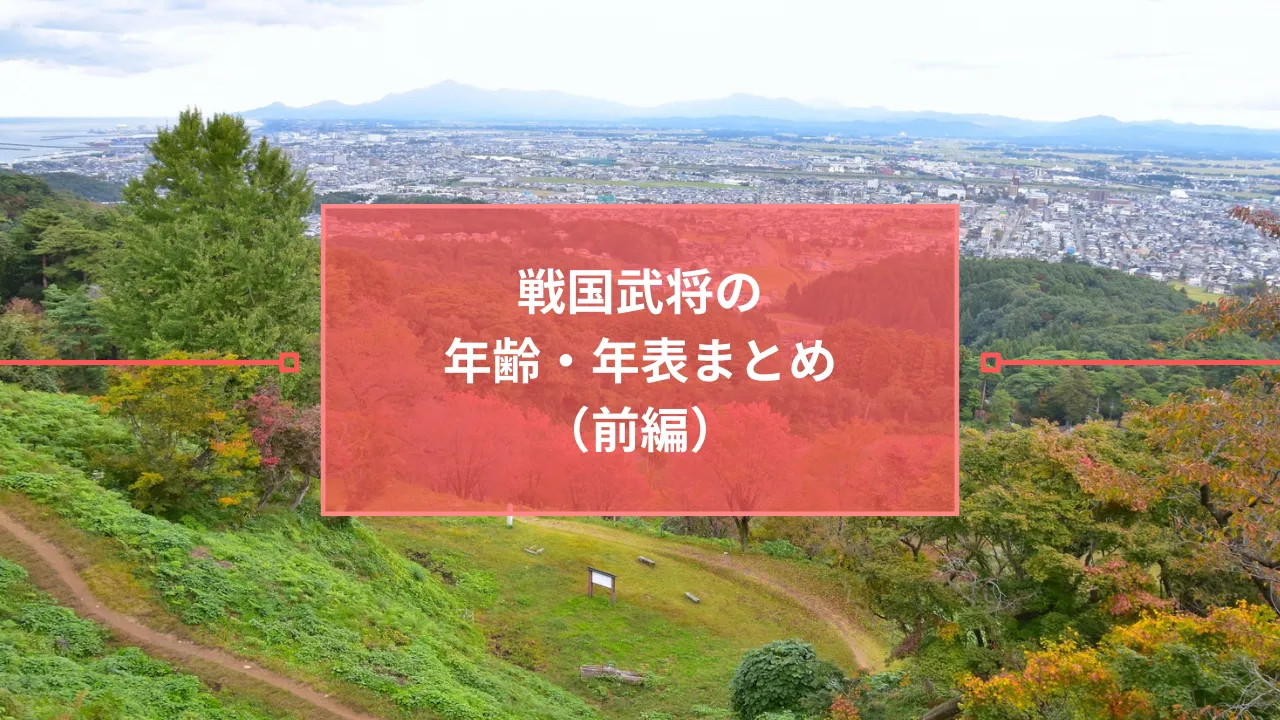-

年表で見る戦国時代!時系列で見る戦国武将の生まれ年&年齢と出来事まとめ(~大坂夏の陣/戦国時代終焉編)
今回のスーパーサイト人ダンディの記事は戦国時代まとめの後半。徳川家康誕生後から戦国時代が終焉した1615年の大阪夏の陣までに誕生した有名な戦国武将や歴史的な出来事を年代別・年功序列にしてまとめています。大河ドラマなどでは年齢が不明瞭ですがこうしてまとめることで何歳差があるのか知ることができたので非常に面白い内容となっています。
目次
- 1 1432年(永享4年)
- 2 1467年(応仁元年)
- 3 1487年(長享元年)
- 4 1493年(明応2年)
- 5 1494年(明応3年)
- 6 1497年(明応6年)
- 7 1515年(永正12年)
- 8 1516年(永正13年)
- 9 1517年(永正14年)
- 10 1519年(永正16年)
- 11 1521年(大永元年)
- 12 1523年(大永3年)
- 13 1528年(大永8年)
- 14 1530年(享禄3年)
- 15 1533年(天文2年)
- 16 1534年(天文3年)
- 17 1535年(天文4年)
- 18 1536年(天文5年)
- 19 1537年(天文6年)
- 20 1538年(天文7年)
- 21 1539年(天文8年)
- 22 1540年(天文9年)
- 23 1541年(天文10年)
- 24 1542年(天文11年)
- 25 1543年(天文12年)
- 26 今日はここまで!
1432年(永享4年)
北条早雲(伊勢 宗瑞)誕生
下剋上ののち、最初の戦国大名ともいわれる北条早雲が誕生したのが1432年(永享4年)です。
現在の神奈川県小田原市にある小田原城を拠点に活躍しました。
注意ポイント
1467年(応仁元年)
| 北条早雲 | 35歳 |
応仁の乱が勃発
室町幕府管領家の家督争いが原因で、細川勝元と山名宗全の勢力争いに発展した。
室町幕府8代将軍足利義政の後継者問題も加わわって、全国に争いが拡大しました。室町時代から戦国時代に変化する原因となった出来事。
内乱が完全に終結するのはこれから11年も先の話です。
1487年(長享元年)
| 北条早雲 | 55歳 |
北条氏綱誕生
最初の戦国大名といわれる北条早雲の子供にして早雲の跡を継いで北条家2代目当主となり活躍しました。
「勝って兜の緒を締めよ」という言葉はこの氏綱の遺言からきていると言われています。
1493年(明応2年)
| 北条早雲 | 61歳 |
| 北条氏綱 | 6歳 |
明応の政変勃発
細川政元が発端となって発生した室町幕府将軍の擁廃立事件。
政変の結果、室町幕府将軍は足利義稙から足利義澄となり、足利将軍家は義稙流と義澄流の二系統に分離することになる。
応仁の乱よりポピュラーではないものの、戦国時代の発端となった出来事とされており近年ではこちらが戦国時代に変化する直接的な原因だったと主張する説があります。
1494年(明応3年)
| 北条早雲 | 62歳 |
| 北条氏綱 | 7歳 |
斎藤道三誕生
美濃の戦国大名。娘であるお濃を信長に嫁がせたため織田信長の義父でもあります。
北条早雲と並んで下剋上大名の典型でもあるが、実の子供である義龍に裏切られ長良川の戦いにて戦死。
1497年(明応6年)
| 北条早雲 | 65歳 |
| 北条氏綱 | 10歳 |
| 斎藤道三 | 3歳 |
毛利元就誕生
中国地方の戦国大名。安芸の国人領主に過ぎなかったが1代で中国地方の覇者となる。
3本の矢の話、西国の桶狭間といわれる厳島の戦い、優秀な3人の息子(隆元・吉川元春・小早川隆景)は有名です。
1515年(永正12年)
| 北条早雲 | 83歳 |
| 北条氏綱 | 28歳 |
| 斎藤道三 | 21歳 |
| 毛利元就 | 18歳 |
北条氏康誕生
北条氏綱の長男で北条家の3代目当主。
近隣大名である武田・今川家と甲相駿三国同盟を結び関東の支配権を確立し、上杉謙信をも退けた猛者。
当時では画期的であり後世に手本になるほどの民生制度を策定し充実を図るなど政治的手腕も発揮、子の北条氏政との共同政治期間を含めると30年以上にもわたり北条家を率いた。
1516年(永正13年)
| 北条早雲 | 84歳 |
| 北条氏綱 | 29歳 |
| 斎藤道三 | 22歳 |
| 毛利元就 | 19歳 |
| 北条氏康 | 1歳 |
北条早雲が相模全域を平定
北条早雲が激戦の末に三浦義同・義意父子を打ち滅ぼし、伊豆に続いて相模全域を平定。
最初の戦国武将として名を馳せる。
こののち、1590年の小田原征伐で豊臣秀吉に滅ぼされるまで、北条家5代にわたり関東を支配していきます。
1517年(永正14年)
| 北条早雲 | 85歳 |
| 北条氏綱 | 30歳 |
| 斎藤道三 | 23歳 |
| 毛利元就 | 20歳 |
| 北条氏康 | 2歳 |
有田中井手の戦い
武田元繁と毛利元就との戦い。毛利元就にとっては初陣となる戦いでもありました。
この戦いの結果、武田元繁は戦死。毛利家の勢力拡大と武田家が弱体化する分水嶺となりました。
ちなみにこの戦いは少数の織田軍が大軍の今川義元を討ち取った桶狭間の戦いに似ていることから後世、「西の桶狭間」と呼ばれています。
毛利元就三大合戦の1つです。
1519年(永正16年)
| 北条早雲 | 死去(87歳) |
| 北条氏綱 | 32歳 |
| 斎藤道三 | 25歳 |
| 毛利元就 | 22歳 |
| 北条氏康 | 4歳 |
今川義元誕生
駿河を中心に活躍した戦国大名。
「海道一の弓取り」の異名をもつ大名で駿河や遠江を中心に三河や尾張の一部にまで支配権を広げ、今川家の全盛期を築き上げた。
武田信玄・北条氏康と甲相駿三国同盟を結び安全を確保し西への領土拡大を目指し尾張に攻め入るも大軍による過信と15歳下の織田信長を見くびった結果、桶狭間の戦いでの奇襲にあって戦死。
1521年(大永元年)
| 北条氏綱 | 34歳 |
| 斎藤道三 | 27歳 |
| 毛利元就 | 24歳 |
| 北条氏康 | 6歳 |
| 今川義元 | 2歳 |
武田信玄誕生
甲斐武田家の当主で守護大名から戦国大名化し甲斐国(現:山梨県)内を統一した武田信虎の長男。
隣国の信濃を中心に駿河や遠江、三河など領土を拡大する中で越後の上杉謙信と5回にわたり川中島で戦った。
領土拡大の傍ら、川の氾濫に苦しむ領民のために現代にも残る信玄堤をつくって氾濫を防ぐなど内政にも手腕を発揮した。
信玄より22歳下で江戸幕府を開き戦国時代を終焉させた徳川家康は三方ヶ原の戦いなど通じて、信玄を高く評価しており後年の家康の手法は信玄を参考にしたと言われています。
1523年(大永3年)
| 北条氏綱 | 36歳 |
| 斎藤道三 | 29歳 |
| 毛利元就 | 26歳 |
| 北条氏康 | 8歳 |
| 今川義元 | 4歳 |
| 武田信玄 | 2歳 |
毛利隆元誕生
毛利元就の長男で毛利家当主ですが元就より先に亡くなったため毛利家の実権を握り率いることはなかったと言われています。
1代で中国地方最大の大名となった元就をはじめ武勇の吉川元春、知略の小早川隆景と優秀すぎる父と弟たちに囲まれ、さらには40歳という若さで死去したことから先述の彼らや子の輝元と比較しても有名とはいえません。
しかし彼の死後毛利家の収入は減少し財政面が傾いたことから、優れた内政・財務手腕と穏やかな性格を武器に毛利家の屋台骨を支えていました。
まさに縁の下の力持ちであり彼の偉大さを死後になって痛感した元春と隆景は一層毛利家に尽くすようになり、毛利両川体制が一層強固になりました。
1528年(大永8年)
| 北条氏綱 | 41歳 |
| 斎藤道三 | 34歳 |
| 毛利元就 | 31歳 |
| 北条氏康 | 13歳 |
| 今川義元 | 9歳 |
| 武田信玄 | 7歳 |
| 毛利隆元 | 5歳 |
明智光秀誕生
恐らく戦国三英傑の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康以外で言えば最も有名な戦国武将のうちの1人。
織田信長の重臣として仕えるが、1582年(天正10年)に本能寺の変で主君信長とその長男信忠を自刃に追い込んだ。
その後安土城以下、信長を作り上げた物を全て壊し天下人として天下統一に向けて邁進しようとするも毛利家と和議を結び中国大返しでUターンしてきた豊臣秀吉に山崎の戦いで敗戦し死去した。
死去したのは本能寺の変で信長を討って天下人となったわずか13日後であり、「三日天下」の語源にもなっています。
注意ポイント
1530年(享禄3年)
| 北条氏綱 | 43歳 |
| 斎藤道三 | 36歳 |
| 毛利元就 | 33歳 |
| 北条氏康 | 15歳 |
| 今川義元 | 11歳 |
| 武田信玄 | 9歳 |
| 毛利隆元 | 7歳 |
| 明智光秀 | 2歳 |
上杉謙信誕生
歴史の教科書に掲載される戦国大名以外では武田信玄と並んで有名な戦国武将の1人。
内乱で荒れていた越後国(現:新潟県)を統一し他国からの救援要請を受けると「儀」の旗印を掲げて出兵、武田信玄や北条氏康など近隣の戦国武将と激戦を繰り広げました。
特に武田信玄との5度に渡る川中島の合戦は有名。また産業を発展させて国の充実を図るなど政治的手腕も発揮しました。
「敵に塩を送る」ということわざは上杉謙信がライバルであった武田信玄に塩を送って助けたことが起源になっています。
吉川元春誕生
毛利元就の次男にして吉川家当主。兄に毛利隆元、弟に小早川隆景を持ち生涯参戦した戦で負けたことのない武勇誉な猛将。
父・元就が吉川家を乗っ取るため毛利家より吉川家に養子に出されて以降、吉川家ばかり優先していたが隆元の死後兄の偉大さを痛感し一層毛利家に尽くした。
弟の隆景と共に毛利両川体制の一翼を担い山陰の司令官として活躍。元就・隆元、2人の死後は幼くして毛利家当主となった隆元の長男で甥の輝元を後見し生涯毛利家を支えました。
1533年(天文2年)
| 北条氏綱 | 46歳 |
| 斎藤道三 | 39歳 |
| 毛利元就 | 36歳 |
| 北条氏康 | 18歳 |
| 今川義元 | 14歳 |
| 武田信玄 | 12歳 |
| 毛利隆元 | 10歳 |
| 明智光秀 | 5歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 3歳 |
小早川隆景誕生
毛利元就の三男で小早川家当主。実兄に内政・財務手腕に長けた毛利隆元と生涯不敗の武勇誉な吉川元春がいます。
兄の元春が山陰地方を担当し隆景は瀬戸内海を中心に山陽の司令官として活躍した。
毛利両川体制の一翼を担って父・元就、兄・隆元を支え、2人の死後は甥・輝元を後見して元春と共に生涯毛利家を支えた。
豊臣政権下では毛利家の家臣という立ち位置は固持したものの徳川家康や前田利家と共に五大老に任命されるなど豊臣秀吉に信頼・重用された。
豊臣秀吉が「東は徳川家康、西は小早川隆景に任させれば安泰」と言い放ったことからも隆景をいかに信頼していたが分かります。
信長・秀吉・家康に一目置かれた軍師である黒田官兵衛は隆景の死後「これでこの国に賢人はいなくなった」と言い放ち、彼の遺言を守らなかったばかりに毛利家は関ケ原の戦いに際し改易の危機を迎えることになります。
1534年(天文3年)
| 北条氏綱 | 47歳 |
| 斎藤道三 | 40歳 |
| 毛利元就 | 37歳 |
| 北条氏康 | 19歳 |
| 今川義元 | 15歳 |
| 武田信玄 | 13歳 |
| 毛利隆元 | 11歳 |
| 明智光秀 | 6歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 4歳 |
| 小早川隆景 | 1歳 |
織田信長誕生
歴史の教科書に掲載される戦国武将で歴史に興味がない人でも必ずは名前は聞いたことがあるであろう有名な戦国武将の1人。
その先見性とカリスマ性を武器に「天下布武」を掲げて天下統一へと邁進。
桶狭間の戦いにて奇襲を行い倍以上の大軍であった今川義元を討ち取ったり、リロードに時間がかかり連射不可能な当時の火縄銃を柵を張り3列構えの鉄砲隊で連射可能にし当時最強と言われた武田の騎馬隊に圧勝した長篠の戦いなど常識に囚われない戦術で他国を圧倒。
また楽市楽座など画期的な内政手腕で領国の充実を図り若年期は尾張1国も平定していなかったが晩年期には既に大国を築いていた武田・上杉・毛利家を圧倒するほどの国力を手に入れた。
そしてついに52歳となる1582年(天正10年)に強国の1つであったライバルの武田家を滅亡させ、上杉・毛利家も屈服寸前まで追い込むなど天下統一まであと1歩まで迫ったが武田家を滅亡させた3か月後に明智光秀に謀反を起こされ、本能寺の変にて長男の信忠と共に自刃して死去した。
1535年(天文4年)
| 北条氏綱 | 48歳 |
| 斎藤道三 | 41歳 |
| 毛利元就 | 38歳 |
| 北条氏康 | 20歳 |
| 今川義元 | 16歳 |
| 武田信玄 | 14歳 |
| 毛利隆元 | 12歳 |
| 明智光秀 | 7歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 5歳 |
| 小早川隆景 | 2歳 |
| 織田信長 | 1歳 |
島津義弘誕生
武勇の誉れ高く「鬼島津」の異名を持ち現代ではその愛称で親しまれている戦国屈指の猛将。剃髪し「維新斎」と号したことから「維新公」という名でも親しまれている。
元々は次男であり先に家督を継いだ兄の義久を弟の歳久・家久とともに支え、兄弟で島津家の勢力拡大に尽力し豊臣秀吉が大名同士の争いを禁止した天下惣無事令を発布した後も勢力拡大に邁進し大友宗麟の領国に攻め込んだ。
その結果、宗麟は秀吉に援軍を頼み先発隊として黒田官兵衛・毛利輝元・吉川元春・小早川隆景などといった黒田・毛利の連合軍と激突し遅れて豊臣秀吉の本隊が到着したこともあって兵力差で形勢不利となり敗北、秀吉の軍門に下った。
豊臣政権下に入ると義久から家督を譲り島津家当主となり、豊臣秀吉の天下統一に協力し朝鮮の役にも従軍するなど豊臣家に貢献した。
関ケ原の戦いでは撤退が遅れて敵軍に囲まれた孤立状態から正面突破を試み領国へ帰還、その際に井伊直政と松平忠吉(家康4男)に手傷を負わせたのは有名な話です。
また義久・義弘・歳久・家久の4兄弟は非常に仲が良く結束も高かったと言われています。
1536年(天文5年)
| 北条氏綱 | 49歳 |
| 斎藤道三 | 42歳 |
| 毛利元就 | 39歳 |
| 北条氏康 | 21歳 |
| 今川義元 | 17歳 |
| 武田信玄 | 15歳 |
| 毛利隆元 | 13歳 |
| 明智光秀 | 8歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 6歳 |
| 小早川隆景 | 3歳 |
| 織田信長 | 2歳 |
| 島津義弘 | 1歳 |
佐々成政誕生
元々は織田信長の家臣として活躍し長篠の戦いでは鉄砲隊を率いて活躍し、後に織田信長の命で前田利家、不破光治と共に府中三人衆として柴田勝家の与力となり越後の上杉家を中心とした北国の武将を相手に戦った。
しかし本能寺の変で織田信長が死去。柴田勝家の味方になるも賤ヶ岳の戦いで勝家が秀吉に敗れて降伏、自国の越中は安堵され改易は免れるました。
しかし小牧・長久手の戦いにて秀吉を裏切り徳川家康についたことで秀吉の怒りを買い家康が秀吉と停戦、家康の説得に失敗したことで再び秀吉に降伏。領地はほぼ全て没収され、御伽衆として秀吉に仕える。
その後九州平定で武功を上げて肥後一国を貰うも地侍一揆が置き鎮圧できなかったことからその責任を取らされて切腹しました。
1537年(天文6年)
| 北条氏綱 | 50歳 |
| 斎藤道三 | 43歳 |
| 毛利元就 | 40歳 |
| 北条氏康 | 22歳 |
| 今川義元 | 18歳 |
| 武田信玄 | 16歳 |
| 毛利隆元 | 14歳 |
| 明智光秀 | 9歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 7歳 |
| 小早川隆景 | 4歳 |
| 織田信長 | 3歳 |
| 島津義弘 | 2歳 |
| 佐々成政 | 1歳 |
豊臣秀吉誕生
織田信長・徳川家康と並び称される戦国三英傑の1人で歴史に興味がない人でも名前くらいは聞きたことがあるであろう最も有名な戦国武将の1人。野戦の得意な家康と反して城攻め特に兵糧攻めを得意とする。
元々農民だが織田信長に見いだされ織田政権下で頭角を現し、信長晩年期には対中国地方司令官として進軍し毛利家と激戦を繰り広げる。
備中高松城を水攻めにし信長の命令通り毛利家を屈服寸前に追い詰めるがその矢先に織田信長が本能寺の変で死去。前方は毛利、後方は明智光秀ということで挟撃されると逆に危うい立場となる。
しかし得意な外交戦略を駆使して織田家の武将が敵国の反撃を受けるなど各地で釘付けにされて動けない中で先んじて毛利と停戦すると中国大返しと言われるとんでもないUターン攻勢を行い、本能寺の変から僅か13日後に明智光秀を山崎の戦いで滅ぼしどの武将よりも早く主君・織田信長の仇を討つ。
その後、清須会議や賤ヶ岳の戦いを経て天下人の地位と信長の築いた広大な領土をほとんどそっくり手中に収め信長の後継者として天下統一事業を推し進め1590年、53歳の時に最後の反対勢力であった北条家を小田原城の戦いで滅ぼしついに天下を統一した。
1538年(天文7年)
| 北条氏綱 | 51歳 |
| 斎藤道三 | 44歳 |
| 毛利元就 | 41歳 |
| 北条氏康 | 23歳 |
| 今川義元 | 19歳 |
| 武田信玄 | 17歳 |
| 毛利隆元 | 15歳 |
| 明智光秀 | 10歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 8歳 |
| 小早川隆景 | 5歳 |
| 織田信長 | 4歳 |
| 島津義弘 | 3歳 |
| 佐々成政 | 2歳 |
| 豊臣秀吉 | 1歳 |
北条氏政誕生
北条家4代目当主。北条氏康の次男として生まれ、長男が早世したために世継ぎとなった。
氏康より家督を継ぎ当主となるが氏康が1571年に死去するまでは二頭政治を行い、死去後の実権を完全に把握し北条家を率いた。
豊臣秀吉が台頭した時代では天下惣無事令を無視し勢力拡大のために真田昌幸が収める信濃など近隣諸国を攻撃。
秀吉からの再三の臣従命令を無視した結果、小田原城の戦いが勃発する。
秀吉は当時では最大規模の約20万以上の大軍で小田原城に進軍、氏政も戦の天才・上杉謙信をも退却せしめた難攻不落の小田原城に籠り、籠城戦の構えをみせました。
氏政は当初20万の大軍ではすぐ食糧が尽きると考え、また伊達政宗・徳川家康が内応していたため援軍が来ると思っていました。
しかし予想に反して秀吉軍は北条家の味方の城を次々と攻略、大量に食糧を買い込んでいたことで食糧切れにならずまた小田原城の目前の石垣山に城を築かれ徹底攻勢の秀吉軍に次第に劣勢となります。
また頼みにしていた伊達政宗は秀吉に臣従、家康も動かず遂に秀吉に降伏し敗北。氏政は切腹、子の氏直は謹慎処分になり1年後に死去し北条家の関東支配は終焉しました。
]父・氏康の基盤を引き継ぎ内政を充実させ北条家の最大勢力範囲を築き上げたのも彼なので決して無能ではありませんが、5代続いた北条家を外交失敗で滅亡させたために愚将扱いさやすいのが残念。
この北条家の敗北によって秀吉の天下統一事業は完成されました。
前田利家誕生
加賀藩の祖として崇められ加賀100万石の礎を築いた人物で妻は才女として有名なまつ(芳春院)。
豊臣秀吉が足軽の頃からの仲で家が隣だったこともあって秀吉の家臣の中ではもっとも古い付き合いだと言われている。
元々は佐々成政らと共に柴田勝家の与力として北陸進軍の一員として従軍する傍らで秀吉が総司令官を務める中国地方進軍の三木城攻めや有岡城攻めにも加わるなど信長の直参家臣としての一面も持っていたと言われる。
本能寺の変の後、賤ケ岳の戦いに際しては旧友の秀吉と直属の上司である勝家との間で苦悩し最初は勝家につくも途中で反旗を翻し秀吉の軍門に入った。
その後は秀吉の天下統一事業に積極的に協力し、小田原城の戦いでは北国勢の司令官として上杉景勝や真田昌幸らを従えて北条家の支城を攻略した。
秀吉と旧友でありその武勇と人柄は家臣団の中で一目も二目を置かれていた利家は五大老や秀頼の後見役に抜擢。秀吉亡き後は福島正則や加藤清正といった武断派の家臣と石田三成といった文治派の仲介にも尽力したが秀吉死去の翌年に秀吉の後を追うように死去した。
本多正信誕生
徳川家康の家臣団では1番の年長者。
三河の一向一揆が勃発すると家康を裏切って一揆側につきその後放浪。
時期は定かではないが放浪の後家康の元に帰参しそれ以降は家康を支え家康が江戸幕府が開くと家康に次いで2代将軍秀忠に従い生涯徳川家を支えました。
1539年(天文8年)
| 北条氏綱 | 52歳 |
| 斎藤道三 | 45歳 |
| 毛利元就 | 42歳 |
| 北条氏康 | 24歳 |
| 今川義元 | 20歳 |
| 武田信玄 | 18歳 |
| 毛利隆元 | 16歳 |
| 明智光秀 | 11歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 9歳 |
| 小早川隆景 | 6歳 |
| 織田信長 | 5歳 |
| 島津義弘 | 4歳 |
| 佐々成政 | 3歳 |
| 豊臣秀吉 | 2歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 1歳 |
長宗我部元親誕生
土佐の国人に過ぎなかったが戦国大名として急成長し、四国にて急速に勢力を拡大した。
その後、天下布武を掲げて天下統一を目指す信長の手が迫るが本能寺の変にて信長が死去。安堵したのもつかの間、信長の天下事業を引き継いだ豊臣秀吉に1585年、元親が46歳の時に四国に侵攻され敗北。
切腹は免れたものの土佐一国に減知されました。
1540年(天文9年)
| 北条氏綱 | 53歳 |
| 斎藤道三 | 46歳 |
| 毛利元就 | 43歳 |
| 北条氏康 | 25歳 |
| 今川義元 | 21歳 |
| 武田信玄 | 19歳 |
| 毛利隆元 | 17歳 |
| 明智光秀 | 12歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 10歳 |
| 小早川隆景 | 7歳 |
| 織田信長 | 6歳 |
| 島津義弘 | 5歳 |
| 佐々成政 | 4歳 |
| 豊臣秀吉 | 3歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 2歳 |
| 長宗我部元親 | 1歳 |
吉田郡山城の戦い
尼子軍3万が毛利家の居城・吉田郡山城に押し寄せたことで起きた毛利元就と尼子晴久の戦い。
局地的な城外戦が展開されたために、一般的には籠城戦の1つとは数えられていない。
毛利軍の手勢は2400人しかおらず大軍の尼子軍に圧倒されるが、大内軍の援軍によって形勢が逆転したことで毛利軍が勝利した。
有田中井手の戦いと並び、毛利元就三大合戦の1つに数えられています。
この戦いで毛利元就の次男・吉川元春が初陣を飾る。
1541年(天文10年)
| 北条氏綱 | 死去(54歳) |
| 斎藤道三 | 47歳 |
| 毛利元就 | 44歳 |
| 北条氏康 | 26歳 |
| 今川義元 | 22歳 |
| 武田信玄 | 20歳 |
| 毛利隆元 | 18歳 |
| 明智光秀 | 13歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 11歳 |
| 小早川隆景 | 8歳 |
| 織田信長 | 7歳 |
| 島津義弘 | 6歳 |
| 佐々成政 | 5歳 |
| 豊臣秀吉 | 4歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 3歳 |
| 長宗我部元親 | 2歳 |
美濃の国盗り
下剋上の末にのし上がった斎藤道三が土岐氏を尾張に追放。
その結果、斎藤道三が美濃を掌握し美濃国主に君臨。美濃の戦国大名として一層、名を馳せるようになる。
武田信虎追放
武田信玄がクーデターを起こし、父親の武田信虎を追放。
今川家が支配する駿河に強制的に隠居させる。
クーデターを成功させた武田信玄は、信虎の跡を継いで武田家当主となる。
1542年(天文11年)
| 斎藤道三 | 48歳 |
| 毛利元就 | 45歳 |
| 北条氏康 | 27歳 |
| 今川義元 | 23歳 |
| 武田信玄 | 21歳 |
| 毛利隆元 | 19歳 |
| 明智光秀 | 14歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 12歳 |
| 小早川隆景 | 9歳 |
| 織田信長 | 8歳 |
| 島津義弘 | 7歳 |
| 佐々成政 | 6歳 |
| 豊臣秀吉 | 5歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 4歳 |
| 長宗我部元親 | 3歳 |
第一次月山富田城の戦い
1540~1541年にかけて勃発した吉田郡山城の戦いの結果、敗亡した尼子は味方が次々と大内に寝返ることに。
尼子から寝返った者を取り込んだ大内軍は吉田郡山城の戦いに勝利した勢いで尼子家の居城・月山富田城に攻め込むも味方の裏切りなどもあり大敗。
撤退の最後尾を務めた毛利軍も壊滅的な打撃をうけ、毛利元就・隆元父子も自害寸前まで追いつめられるも、九死に一生を得て居城・吉田郡山城に帰還する。
この戦いは結果的に大内家の衰退と尼子家の最盛期の分水嶺となりました。
1543年(天文12年)
| 斎藤道三 | 49歳 |
| 毛利元就 | 46歳 |
| 北条氏康 | 28歳 |
| 今川義元 | 24歳 |
| 武田信玄 | 22歳 |
| 毛利隆元 | 20歳 |
| 明智光秀 | 15歳 |
| 上杉謙信・吉川元春 | 13歳 |
| 小早川隆景 | 10歳 |
| 織田信長 | 9歳 |
| 島津義弘 | 8歳 |
| 佐々成政 | 7歳 |
| 豊臣秀吉 | 6歳 |
| 北条氏政・前田利家・本多正信 | 5歳 |
| 長宗我部元親 | 4歳 |
徳川家康誕生
戦国三英傑に1人であり最も有名な戦国武将。
幼少時は長らく今川・織田の人質生活を送り、今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗れ戦死すると完全に独立し義元死去の混乱に乗じて三河・遠江を抑えた。
その後は早くに織田信長と同盟を結び盟友として活躍。本能寺の変後は豊臣秀吉と小牧・長久手の戦いで対立。局地戦とはいえ秀吉に唯一に黒星をつけて戦いに勝利する。
その後秀吉からの再三の臣従の催促を無視するも実妹次いで実母を人質に送ってきたことでついに屈服し秀吉の軍門に下った。豊臣政権下では破格に地位で優遇され、家康もまた秀吉の天下取りを積極的に支えた。
1598年45歳の時に豊臣秀吉が死去すると天下を狙い、1600年、57歳の時に石田三成いか西軍に組した諸大名を関ヶ原の戦いで蹴散らし天下を掌握。
1603年60歳の時に征夷大将軍に任命され江戸幕府を開き、1605年、62歳の時に三男・徳川秀忠に征夷大将軍を譲り江戸幕府の支配体制と将軍世襲を確立した。
秀忠に征夷大将軍を譲った後は大御所として権勢を振るい、1614年に大阪冬の陣を翌年1615年には大阪夏の陣で豊臣秀吉の遺児・豊臣秀頼を攻めて豊臣家を滅ぼし応仁の乱より続いた戦国時代を終焉させ江戸幕府260年の泰平の世を築いた。
今日はここまで!
最初の戦国武将と言われる北条早雲から戦国時代を終焉させ260年もの太平の世の礎を築いた徳川家康までを紹介しました。
これ以降も戦国時代が終焉した1615年の大阪夏の陣まで多くの戦国武将がこの世に生まれましたがそれは近日中に公開する次の記事で紹介しますね。
ここで紹介した戦国武将以外にもたくさんの戦国武将がいますが上げるときりがないので有名どころだけをピックアップしています。
この記事をきっかけに歴史に興味を持ってくれれば幸いです。
-

年表で見る戦国時代!時系列で見る戦国武将の生まれ年&年齢と出来事まとめ(~大坂夏の陣/戦国時代終焉編)
今回のスーパーサイト人ダンディの記事は戦国時代まとめの後半。徳川家康誕生後から戦国時代が終焉した1615年の大阪夏の陣までに誕生した有名な戦国武将や歴史的な出来事を年代別・年功序列にしてまとめています。大河ドラマなどでは年齢が不明瞭ですがこうしてまとめることで何歳差があるのか知ることができたので非常に面白い内容となっています。